自動車保険
自動車保険の損害率とは?2025年制度改正と保険料への影響を徹底解説

損害率とは?自動車保険における基本的な仕組み

損害率とは、保険会社が契約者から集めた保険料に対して、実際に事故などで支払った保険金の割合を示す指標です。
損害率の計算式
損害率 = (支払保険金 ÷ 収入保険料) × 100
具体例
例えば、自動車保険で100億円の保険料を集め、80億円を保険金として支払った場合、損害率は80%となります。この数字が高いと「事故や災害での支払いが多い」ということであり、逆に低ければ「保険会社に余裕がある」という状態を意味します。
自動車保険の損害率の特徴

自動車保険の損害率は、他の保険商品に比べて変動が大きい傾向があります。背景にはさまざまな要因があります。
交通事故の発生件数と規模
交通事故の件数や事故の規模は、そのまま保険金の支払い額に直結します。事故が多ければ損害率は高まりやすくなります。
自然災害による車両被害
台風や大雨、地震といった自然災害で多くの車両が損害を受ければ、車両保険の支払いが増加し、損害率を押し上げます。
修理費・医療費の上昇
近年は自動ブレーキなど先進安全技術の普及で事故件数自体は減少傾向にあります。しかし、部品価格や修理費用の上昇により、一件あたりの支払い額が増え、損害率は下がりにくい状況です。
損害率と自動車保険料の関係

損害率が高止まりすると、保険会社は将来の安定経営を維持するために保険料を引き上げざるを得ません。例えば、交通事故や自然災害によって支払いが急増した場合、翌年度の自動車保険料改定に反映されます。逆に、損害率が安定していれば保険料は据え置かれたり、割引制度の拡大につながる場合もあります。
2025年からの制度変更:軽自動車の型式別料率クラス拡大

2025年1月1日以降の契約から、自家用軽四輪乗用車(軽自動車)の型式別料率クラスが従来の3クラスから7クラスに拡大されました。
改定の背景
軽自動車の普及拡大や車種ごとの安全性能の差が大きくなり、従来の区分では十分にリスクを反映できなくなったためです。事故率や修理費用に応じた、より精緻な料率体系が必要になりました。
改定の影響
損害保険料率算出機構の資料によると、クラス間の差はおおむね約1.1倍、最も安いクラスと最も高いクラスの差は約1.7倍となります。これにより、安全性能が高く事故率が低い車種は保険料が下がりやすく、逆にリスクが高い車種は保険料が上がる可能性があります。
損害率の動向と今後の見通し

損害保険料率算出機構が公表している統計では、自動車保険の損害率は自然災害の多発や修理費の高騰で高止まり傾向にあります。特に台風被害が大きかった年には車両保険の支払いが急増し、損害率が大幅に上昇しました。今後も災害リスクや車両の高度化による修理費増加が続けば、損害率は保険料に影響を及ぼし続けると考えられます。
加入者にできる工夫と備え
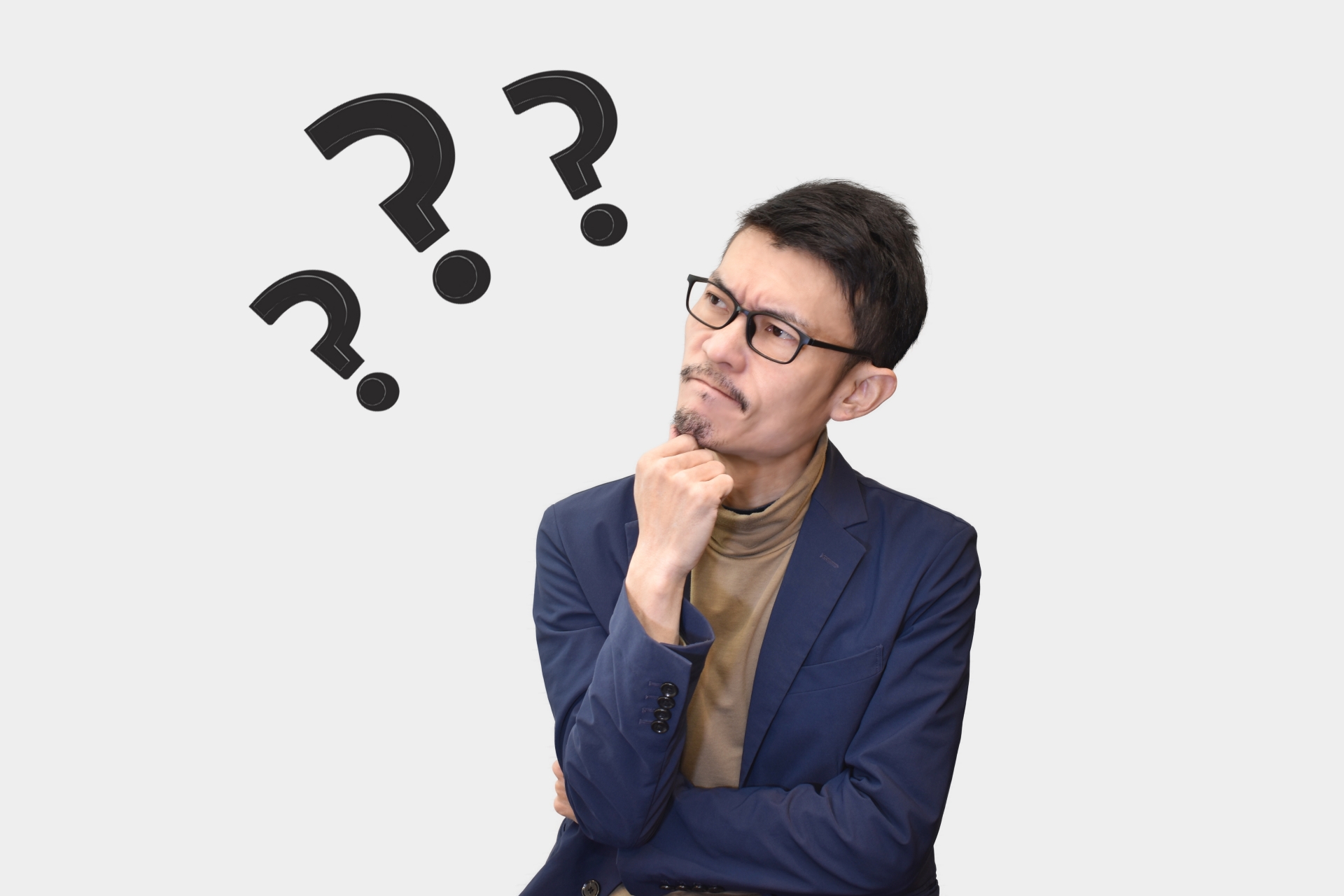
損害率や制度改定は個人でコントロールできませんが、保険料の上昇リスクに備える方法は存在します。
安全運転の徹底
事故を未然に防ぐことが、結果的に損害率を下げ、将来的な保険料負担の軽減につながります。
補償内容の見直し
車両保険や特約を必要最小限に整理し、ライフスタイルに合った保障内容を選ぶことが大切です。
契約の工夫
長期契約(複数年契約)やインターネット割引、ゴールド免許割引などを活用すれば、保険料を抑えることが可能です。
まとめ
自動車保険の損害率は、事故件数や自然災害、修理費の動向に大きく左右される指標であり、保険料改定に直結します。さらに2025年からは軽自動車の型式別料率クラス制度が改定され、車種ごとのリスクがより正確に反映されるようになりました。契約者にとって損害率は見えにくい数字ですが、その仕組みを理解しておくことで、将来の保険料変動に備え、無理のない補償選びができるようになります。
参考情報
・損害保険料率算出機構「自動車保険 型式別料率クラスの仕組み(2025年1月1日以降)」
https://www.giroj.or.jp/common/pdf/vehicle_model_2025.pdf
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



