自動車保険
自動車保険の「全損」と「分損」とは?保険金の支払い基準と時価額の仕組みを解説

本記事では、全損・分損の定義や保険金の支払い方式、時価額の算定方法、事故車の処分方法まで、実用性とSEOを両立させてわかりやすく解説します。
車両保険における「全損」と「分損」の違い

車両保険では損害の程度に応じて「全損」または「分損」に分類され、この判断が受け取れる保険金に直結します。
全損とは何か
「全損」には以下の2つがあります:
・物理的全損:修理不可能なほどの損壊
・経済的全損:修理は可能でも、修理費が時価額を上回る場合
例:時価額が80万円の車に対し100万円の修理費がかかると見積もられた場合、経済的全損に該当します。
分損とは何か
「分損」は修理可能で、修理費が時価額より低い損害を指します。バンパーの破損などが一般的な例で、修理費そのものが保険金の基準になります。
全損時・分損時の保険金の支払い方式

全損時の保険金
全損と判断された場合、支払われる保険金の上限は「事故発生時点の車両時価額」です。修理費が高額でも市場価値以上は補償されません。
分損時の保険金
分損時は修理費が補償対象ですが、契約に定められた免責金額を差し引かれます。例:修理費50万円、免責金額5万円→支給額は45万円です。
時価額の算定方法と調べ方
「時価額」とは事故時点での車の市場価値です。保険会社は有限会社オートガイドの「自動車価格月報(レッドブック)」を参考に算定します。消費者が自ら目安を確認するには、中古車販売サイトや査定サービスの利用が有効です。
中古車相場と時価額のズレが生じる理由

中古車販売価格には業者の利益や整備費などが含まれており、保険会社の時価額より高くなることがあります。このため、買い替え時に補償額との差で戸惑うことがある点に注意しましょう。
免責金額の仕組み

免責金額は、契約者が事故時に自己負担する金額です。高く設定するほど保険料は下がりますが、事故時の負担も重くなるため、設定は慎重にしましょう。
交渉時の注意点
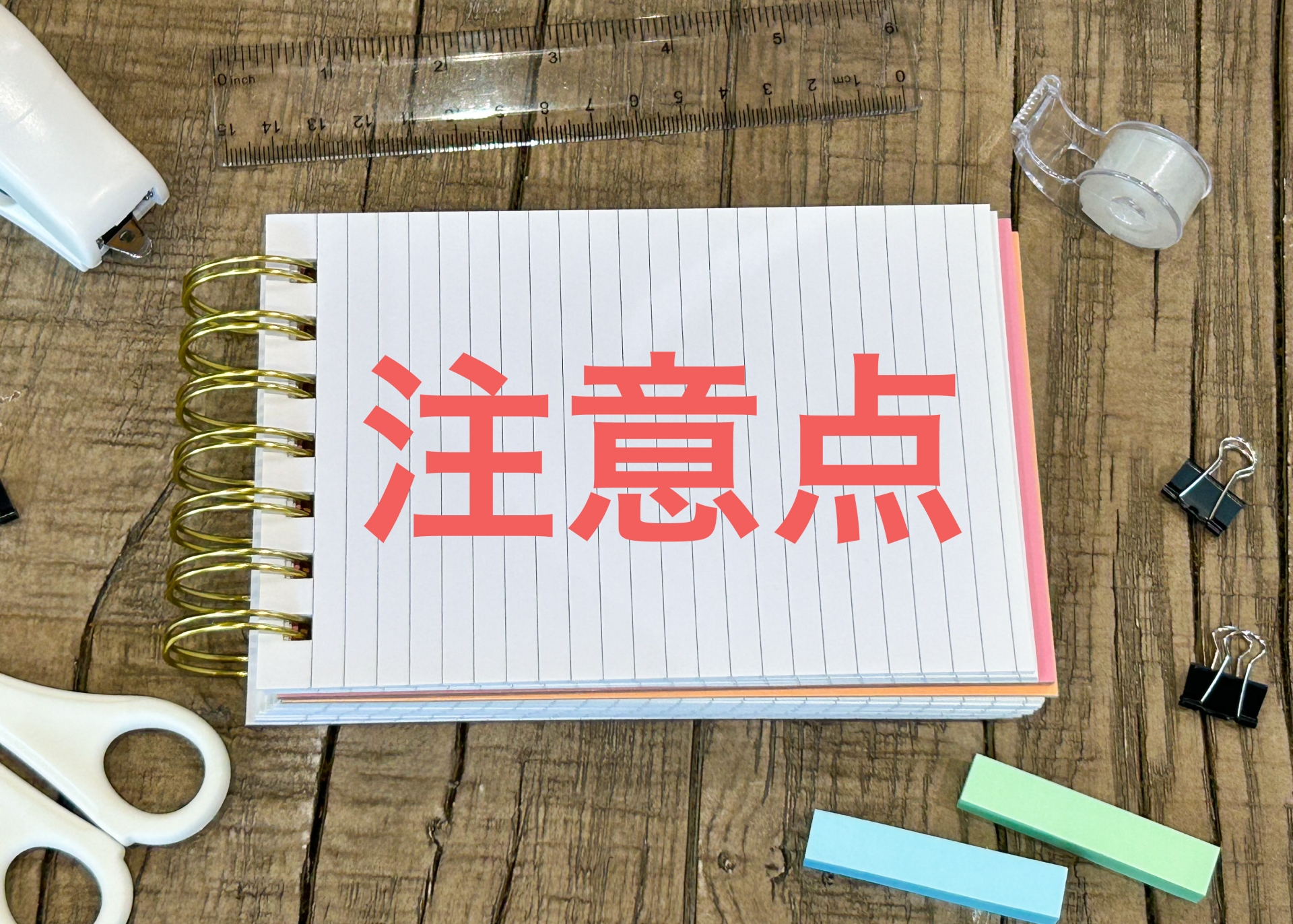
提示された判断や金額に納得できない場合には、修理工場や査定業者の資料をもとに交渉してください。それでも解決しない場合は、公的な「そんぽADRセンター」に相談することが可能です。
事故前後の行動チェックリスト

事故前にすべき準備
・車両保険の約款で全損・分損の基準を確認
・時価額を自分で調べて目安を把握
・免責金額の設定を見直しておく
事故後に確認するべきポイント
・修理見積書を取得し内容を精査
・保険会社の時価額根拠を確認
・中古車市場と比較し妥当性を検討
・資料を用いて交渉に備える
事故車・全損車の処分方法

全損判定の車でも次の方法があります:
・廃車手続き(抹消登録)
・事故車買取業者へ売却(部品取り需要など)
・保険会社提携業者に引き取りを依頼
事故車でも部品に価値がある場合が多く、買取によって廃車以上の利益が得られることもあります。
まとめ
「全損」とは修理不能または修理費が時価額を上回る状態、「分損」とは修理可能で修理費が時価額未満を指します。全損では事故時点の時価額が、分損では修理費から免責金額を差し引いた額が補償されます。時価額はレッドブックに基づいて算定されること、事故車の処分方法を知っておくことが、事後対応をスムーズにします。
参考情報
金融庁|保険会社向けの総合的な監督指針(令和7年4月、HTML版)
金融庁|監督指針 II-4 業務の適切性に関する評価項目
金融庁|相談窓口のご案内(そんぽADRセンターなど)
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



