生命保険
生命保険の「無選択型保険」とは?持病がある人向けの保険
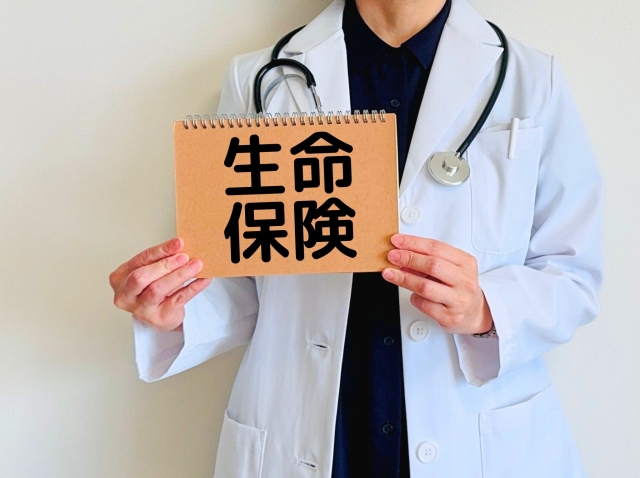
「健康告知なしで入れる保険があるって聞いたけど、どんな保険なの?」
生命保険は、契約時に健康状態を告知する義務があるため、持病がある方や、過去に大きな病気を経験された方は、加入を諦めてしまうこともあるかもしれません。しかし、健康状態に不安がある方でも加入できる「無選択型保険」という商品があります。
この記事では、無選択型保険の仕組みとメリット・デメリットを解説します。告知義務がない代わりに保険料が割高になる理由を詳しく掘り下げ、他の引受基準緩和型保険との違いまで。持病があっても生命保険への加入を諦めたくない方へ、賢い保険選びのヒントを提案します。
無選択型保険の仕組みとメリット・デメリット

無選択型保険とは、その名の通り、健康状態についての告知や診査が不要で、一定の条件を満たせば加入できる生命保険です。
告知義務がない仕組み
告知義務がない:
過去の病歴や現在の健康状態について、保険会社に告知する必要がないため、健康に不安がある方でも加入しやすいのが最大の特徴です。
保険料が割高な理由:
・告知がない分、保険会社は加入者のリスクを個別に判断できません。そのため、健康な人から健康に不安がある人まで、すべての人を一つのグループとしてリスクを評価し、保険料を設定します。
・結果として、健康な人も、持病がある人も、一律で保険料が割高になります。
メリット
1.告知義務がない:
健康状態に自信がない方や、過去の病歴が複雑で告知が難しい方でも、安心して加入できます。
2.加入のハードルが低い:
年齢制限や、持病による加入の可否を気にすることなく、一定の条件を満たせば加入できます。ただし、入院中や医師から治療を勧められている場合は、申し込みができないなどの制限があります。
デメリット
1.保険料が割高:
健康な人が加入した場合でも、一般的な生命保険に比べて保険料が割高になります。
2.保障内容が限定的:
死亡保障に限定されるなど、保障内容がシンプルなものが多く、医療特約などを付加できない場合があります。
3.待機期間と支払削減期間:
無選択型保険には、保障開始までに「待機期間」が設けられていること、そして加入後一定期間は保障額が減額される「支払削減期間」があるため、注意が必要です。
他の引受基準緩和型保険との違い:待機期間と保障内容の比較
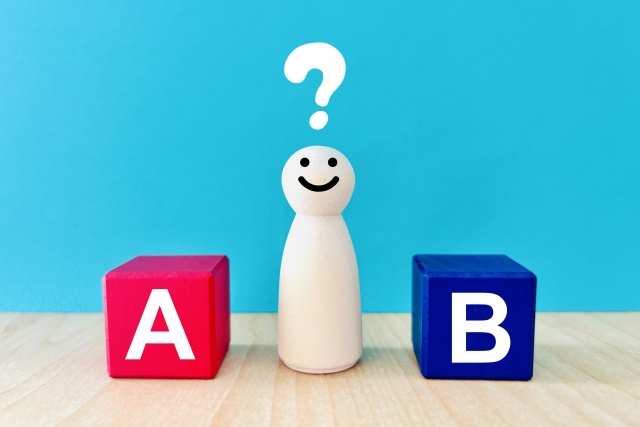
持病がある人向けの保険には、無選択型保険以外にも「引受基準緩和型保険」があります。
引受基準緩和型保険
仕組み:
・告知項目を少なくし、簡単な質問に答えるだけで加入できる保険です。
・無選択型保険よりも保険料は安価ですが、告知義務は存在します。
告知の例:
以下のいずれも「いいえ」なら加入できる・・など。
・「過去3ヶ月以内の入院・手術の有無」
・「過去2年以内の特定の病気による入院・手術の有無」
・「過去5年以内の特定の病気の診断・治療の有無」
無選択型保険と引受基準緩和型保険の比較
告知義務:
・無選択型保険は、告知義務なし。
・引受基準緩和型保険は、告知義務あり(ただし、項目が少ない)。
保険料:
無選択型保険の方が、引受基準緩和型保険に比べて保険料が割高です。
保障開始までの期間:
待機期間:
・引受基準緩和型医療保険には、基本的に待機期間はありません。(※がんに関する特約には、91日程度の待機期間があるのが一般的です。)
・一方、無選択型保険では、死亡保険の場合2年間、医療保険の場合は約3ヶ月(90日間)の待機期間が設けられています。
支払削減期間:
・引受基準緩和型保険: 加入後1年以内は契約した保険金の半額のみ支払いとなるケースが一般的です。
・無選択型保険: 加入後2年以内は、支払った保険料相当額のみの支払い(災害死亡を除く)となるケースが一般的です。
まとめ:無選択型保険は「最後の選択肢」
無選択型保険は、健康上の理由で一般的な生命保険や引受基準緩和型保険にも加入できない方にとっての「最後の選択肢」です。
メリット:
告知義務がなく、一定の条件を満たせば加入できるという安心感があります。
デメリット:
保険料が割高であること、保障内容が限定的であること、そして待機期間や支払削減期間があることを理解しておきましょう。
この記事を参考に、ご自身の健康状態やライフプランに合った最適な保険を選び、安心して日々の生活を送りましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



