火災保険
火災保険の保険金請求に必要性は?罹災証明書の取得方法と注意点

突然の火災や自然災害で自宅が被害を受けたとき、多くの方が不安に思うのは「保険金は支払われるのか」「必要書類は何か」という点です。その中でよく耳にするのが罹災(りさい)証明書ですが、実際には火災保険の請求に原則不要とされています。
ただし保険会社によっては提出を求められる場合もあり、さらに税金の減免や公的支援制度では必須書類となります。この記事では、火災保険との関係、公的支援制度での役割、取得方法や申請期限・有効期限まで整理し、安心して手続きを進められるよう解説します。
罹災証明書の役割:火災保険と公的支援での違い

罹災証明書は、市区町村が災害による住家被害を調査・認定して交付する公的書類です。
火災保険との関係
首相官邸によれば、民間の火災保険や地震保険などの請求では罹災証明書は原則不要です。ただし、保険会社によっては客観的証拠として提出を求める場合があるため、確認が必要です。
公的支援制度との関係
税金の減免、義援金・見舞金、各種支援金の申請には罹災証明書が必須となるケースが多く、生活再建のために非常に重要な書類です。
罹災証明書の被害区分

現在の被害区分は6段階で認定されます。
・全壊
・大規模半壊
・中規模半壊
・半壊
・準半壊
・準半壊に至らない(一部損壊)
出典:内閣府 災害に係る住家の被害認定
罹災証明書の取得方法と流れ

罹災証明書の取得は、以下の流れで進めていきます。
・市区町村役場の窓口で申請(防災課・危機管理課など)
・本人確認書類や被害写真を提出
・自治体職員による現地調査
・調査結果に基づき証明書を交付
注意:修繕や解体を行っている途中、または工事後に罹災証明書を申請することは原則できません。必ず着工前に申請が必要です。
火災の場合の申請先

火災による建物被害の場合は、市区町村ではなく消防署で「り災証明書」が交付されます。自然災害と火災とで申請窓口が異なる点に注意してください。
自己判定方式の利用条件
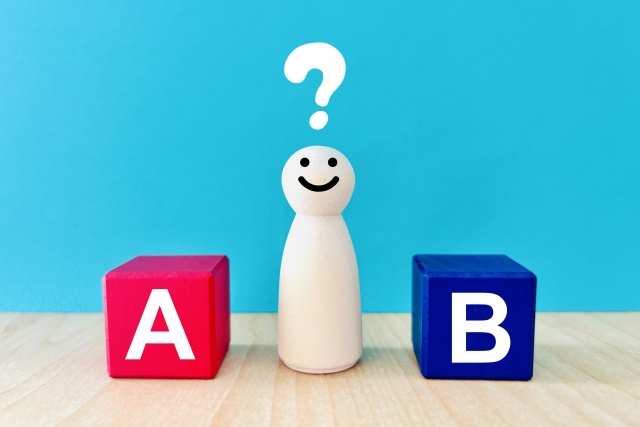
大規模災害時には、罹災証明書の交付において自己判定方式が導入されることがあります。
これは被災者自身が撮影した写真を提出し調査を省略する方式ですが、利用できるのは「準半壊に至らない(一部損壊)」で被害割合10%未満といった軽微な場合に限定されます。
出典:香川県 三木町 「罹災証明書」と「被災証明書」について
申請時に必要な主な書類
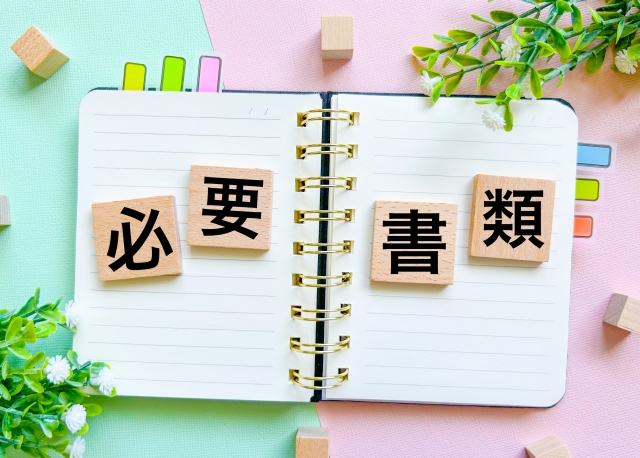
罹災証明を申請する場合、主に以下の書類が必要です。自治体によって異なる可能性があるため、必ずご確認ください。
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・印鑑または署名
・被害写真(全体・部分・細部)
・家屋の所在地を示す書類(固定資産税通知書など)
・修理見積書(あれば望ましい)
・代理人申請の場合は委任状と代理人の本人確認書類
発行期間・有効期限・申請期限

罹災証明書は、発行期限・有効期限・申請期限があります。それぞれ自治体によって異なるため、こちらも事前に確認することをおすすめします。
発行期間(申請してから証明書が手元に届くまでの所要期間):軽微な被害なら数日〜1週間程度、大規模災害では1か月以上かかることもあります。
有効期限:災害発生日から2週間〜1か月程度が一般的(大規模災害では延長あり)。
申請期限(証明書の申請ができる期限):被災から1か月以内に限定する自治体が多いため、早めの申請が必要です。
被災証明書との違い

被災証明書は、住家以外の工作物(物置・倉庫・納屋等)、住家の付帯物(雨樋・カーポート・塀・門扉等)、動産(店舗の商品・施設の機械・車など)、さらに人的被害などを対象とした証明書です。
被災証明書は原則即日交付が可能である一方、罹災証明書は現地調査が必要で発行まで時間がかかる点も大きな違いです。
法的根拠と二次調査
災害対策基本法第90条の2により、市町村長は申請があれば被害調査を行い罹災証明書を交付する義務があります。
認定結果に不服がある場合には二次調査を申請し、再調査を受けることも可能です。
出典:第1章 制度概要 - 内閣府防災情報
まとめ:罹災証明書は役割を理解し早めに行動を
罹災証明書は火災保険請求に必ず必要ではないものの、公的支援や税制優遇には不可欠です。
火災の場合は消防署での「り災証明書」、自然災害の場合は市区町村役場と、窓口が異なる点にも注意してください。
申請期限・有効期限はいずれも短いため、災害後はできるだけ早く申請を行いましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



