火災保険
火災保険の「時価」と「新価」の違いとは?保険金への影響を解説

火災保険を契約するときに必ず確認しておきたいのが「時価」と「新価」の違いです。同じ建物や家財でも評価方法によって補償額が大きく変わり、実際に受け取れる保険金に差が生じます。
本記事では時価評価額と新価(再調達価額)の違いを整理し、保険金支払いに与える影響を解説します。
火災保険における「時価評価額」の定義
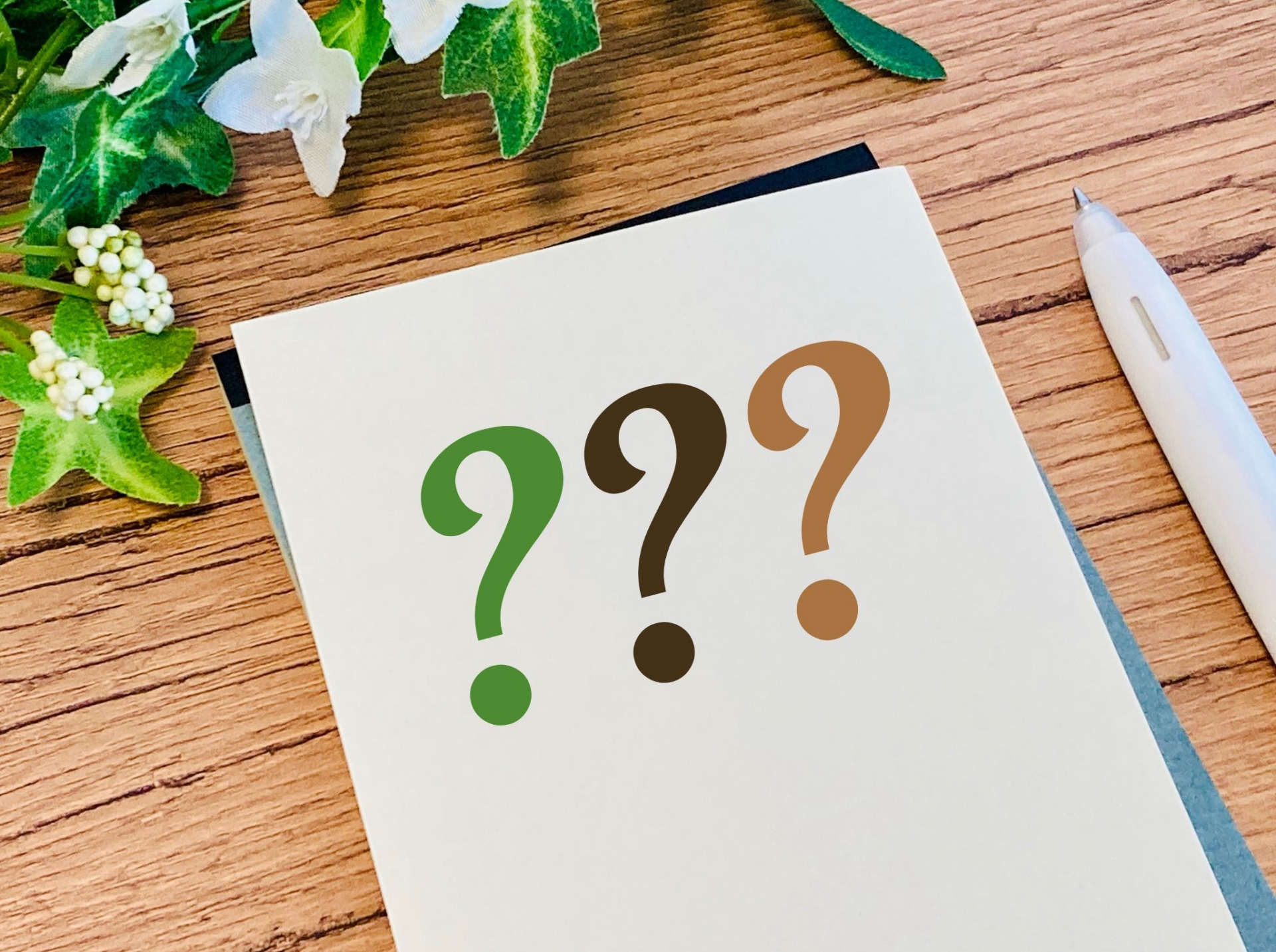
時価とは、対象となる建物や家財を評価した際の「現在の価値」を意味します。購入当初の価格から経過年数による劣化や使用による価値の減少を差し引いた金額です。
火災保険における時価評価額は、事故時点で同じものを売買した場合の市場価値に近いものとされ、修理や再購入の費用を完全にはカバーできないケースが多い点に注意が必要です。
さらに注意したいのは、古い火災保険契約の多くが時価契約となっている点です。特に1998年の保険料率自由化以前や2000年頃までの長期契約では、最長36年契約といった形で時価が採用されているケースがあり、補償が十分でないまま継続している可能性があります。
「新価(再調達価額)」との違いを比較

新価(再調達価額)とは、事故が発生した時点で同等の建物や家財を「新たに購入・建築するために必要な金額」を指します。
簡単にいえば、「新品を買い直すための金額」です。時価と違って減価償却を考慮しないため、より実際の再建・再取得に近い補償を受けられます。
現在では、この新価方式が契約の主流であり、多くの保険会社で時価契約の新規受付は停止されています。中古住宅の場合でも、新築と同様に「同規模・同程度の住宅を再建するために必要な金額」が新価として設定されるため、「築年数が古いから補償額が少なくなる」ということはありません。
時価と新価で保険金の支払額はどれくらい変わる?

例えば、築20年の住宅を考えた場合、建築当初は2,000万円の価値があったとしても、現在の時価評価額は劣化や耐用年数を踏まえ1,000万円程度と見積もられることがあります。
一方で新価は、同等の住宅を再建築する費用として2,000万円を基準に算定されます。つまり、同じ火災でも時価契約の場合は半額程度しか補償されない可能性があり、修繕や建替えに不足が生じることになります。
さらに近年は物価上昇の影響も無視できません。例えば、20年前に2,000万円で建築した住宅でも、現在同等の住宅を再建築するには2,500万円程度必要になるケースもあり、再調達価額は上昇傾向にあります。この差は契約方式によって補償の充実度に大きく影響します。
この違いは火災保険だけでなく、地震保険にも影響します。地震保険は火災保険の保険金額を基準に設定されるため、火災保険が時価契約だと地震保険の支払いも少なくなり、大規模災害時に補償不足となるリスクがあります。
火災保険では、建物や家財の評価方法として「時価」と「新価(再調達価額)」があり、どちらを選ぶかにより受け取れる保険金に大きな差が生じます。この仕組みについては、総務省消防庁が運営する防災教材でも解説されています。
総務省消防庁 防災・危機管理eカレッジ 「火災保険加入の際の注意点(2)」
家財の評価も時価・新価が選択可能
火災保険の対象は建物だけでなく家財も含まれます。家財についても「時価」と「新価」の評価方法があり、所有している家財の合計金額を積算する方法が基本です。
また、日本損害保険協会が示すように、世帯主の年齢や家族構成に応じて平均的な評価額を目安とする簡便な方法も用意されています。
定期的な見直しの重要性
火災保険の契約期間は、2022年10月以降は最長5年となっていますが、それ以前は10年や最長36年といった長期契約も存在しました。古い契約をそのまま継続している場合は、補償が不十分なままになっている可能性があります。
また、再調達価額は一般的に時間の経過とともに上昇し、時価は下落する傾向があります。物価変動の影響もあるため、契約を定期的に見直すことが重要です。
適正な保険金額設定のポイント
現在販売されている火災保険は再調達価額ベースの実損払い方式が主流です。これは実際に被った損害額がそのまま支払われる仕組みであり、補償の実効性を高めています。ただし、契約時に設定する保険金額が適正でなければ十分な補償は受けられません。
保険価額より少ない金額で契約することを一部保険といい、この場合は「比例てん補」が適用され、損害額全体が支払われず一部のみの補償となります。
逆に保険価額を超えて契約することを超過保険といい、保険料を余分に払っても超過部分は支払われません。いずれも損害時に不利になるため、適正な保険金額を設定することが大切です。
最新動向:火災保険の2025年問題と改定情報
火災保険を取り巻く環境は近年大きく変化しています。特に注目すべきは火災保険の2025年問題です。2015年10月から2022年9月末までに10年契約をした保険が、2025年以降に一斉に更新時期を迎えます。この際、多くの契約者が大幅な保険料値上がりに直面すると予測されています。
加えて、2024年10月には参考純率の全国平均が13.0%引き上げられました。これは過去最大の改定幅であり、この10年間で5回目の改定です。さらに水災リスクについては、市区町村単位で5段階に細分化され、最大で約1.2倍の料率格差が生じる仕組みとなりました。
実際、2015年頃と比較すると2025年時点の保険料は1.3倍から2倍に達しているケースも珍しくありません。背景には、自然災害の激甚化により火災保険が恒常的に赤字収支となっている構造的課題があります。契約者にとっては、保険料負担増が避けられない状況です。
こうした状況を踏まえ、契約内容の見直しでは、地域の水災リスクを把握できるハザードマップの確認が不可欠です。市区町村ごとにリスクが異なるため、住まいの立地条件を踏まえて適切な補償を選ぶことが求められます。
まとめ:保険選びでは時価・新価のどちらを選ぶかが重要
火災保険の補償内容を理解するうえで時価と新価の違いは非常に重要です。現在は新価契約が標準であるものの、1998年以前の契約や長期の古い火災保険では時価契約のまま放置されているケースも少なくありません。
さらに、2025年には多くの契約者が更新を迎え、過去最大の保険料引き上げや水災リスク細分化の影響を受ける可能性があります。
火災保険は建物だけでなく家財も対象であり、評価方法や契約金額の設定によって補償額は大きく変わります。保険証券には「時価」か「新価」かが必ず記載されていますので、契約が古く不明な場合は保険会社や代理店に確認しましょう。
特に2000年以前に契約し、長期間見直しをしていない方は、早急に契約内容の確認と見直しを行うことを強くおすすめします。 家計の負担とリスクのバランスを考え、定期的に見直しを行うことが大切です。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



