公的年金制度
年金保険料の免除・猶予制度を解説:もしもの時の手続きと将来への影響

病気や失業、経済的困難など、もしもの時に年金保険料の支払いが難しい場合でも、慌てる必要はありません。国民年金には「免除・猶予制度」という救済措置が用意されています。この記事では、制度の利用方法と、将来の年金受給額への影響を詳しく解説します。
はじめに:保険料を払えない時のNG行動と正しい対応

国民年金保険料の支払いが困難になった時、最もやってはいけないのが「何もせずに放置してしまうこと」です。保険料を未納のままにしておくと、以下のような深刻なリスクが発生します。
・老齢年金の受給資格を失う可能性がある
・障害を負った際に障害基礎年金を受け取れない
・死亡した場合に遺族基礎年金が支給されない
・延滞金が発生し、財産が差し押さえられる場合もある
一方、正しい対応は免除・猶予制度の申請を行うことです。制度を利用すれば、受給資格期間に算入されるため、将来の年金受給権を確保できます。障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格も維持されるため、万が一の事態にも備えられます。
国民年金保険料の免除制度とは?
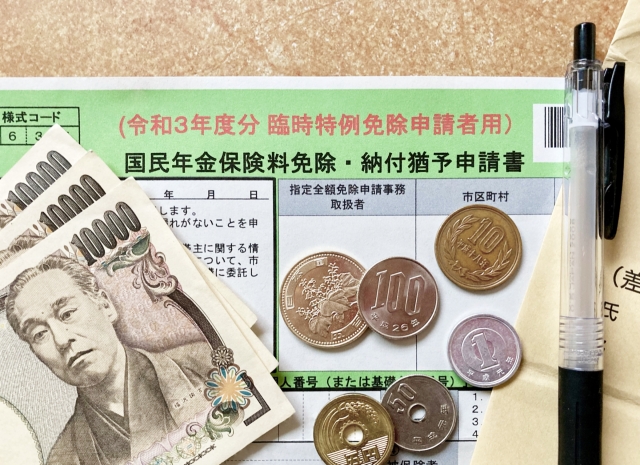
免除制度は、経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の全部または一部が免除される仕組みです。
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の仕組み
免除制度には、所得に応じて4つの段階があります。
・全額免除
保険料が全額免除され、年金の受給資格期間に算入されます。将来受け取る年金額は、保険料を全額納付した場合の2分の1として計算に反映されます。
・4分の3免除
保険料の4分の3が免除され、4分の1を納付する必要があります。年金額は保険料を全額納付した場合の8分の5として反映されます。
・半額免除
保険料の2分の1が免除され、2分の1を納付する必要があります。年金額は保険料を全額納付した場合の4分の3として反映されます。
・4分の1免除
保険料の4分の1が免除され、4分の3を納付する必要があります。年金額は保険料を全額納付した場合の8分の7として反映されます。
なお、一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間として扱われるため注意が必要です。
免除の承認基準(所得、失業など)
免除の承認は、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)に基づいて審査されます。
所得基準の目安
・全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下
・4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下
・半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下
・4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下
例えば、扶養親族が1人の単身世帯の場合、全額免除の所得基準は102万円以下となります。
失業等による特例免除
失業・倒産・事業の廃止などで仕事を失った方は、前年所得の金額にかかわらず免除を受けることができます。ただし、配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除が承認されないこともあります。申請には雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票のコピーなどが必要です。
また、震災、火災、風水害などの災害により、財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合にも、特例免除の申請が可能です。
免除された期間の年金額への反映方法
免除を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間に算入されます。受給資格期間とは、10年以上あれば年金を受給できるという期間のことです。
ただし、年金額の計算では以下のように反映されます。
・全額免除期間:保険料を全額納めた場合の2分の1(平成21年3月以前は3分の1)
・4分の3免除期間:保険料を全額納めた場合の8分の5(平成21年3月以前は2分の1)
・半額免除期間:保険料を全額納めた場合の4分の3(平成21年3月以前は3分の2)
・4分の1免除期間:保険料を全額納めた場合の8分の7(平成21年3月以前は6分の5)
例えば、全額免除の承認期間が2年間ある場合、老齢基礎年金の年額は約2万円程度少なくなります。
国民年金保険料の納付猶予制度とは?

猶予の仕組みと承認基準(所得、学生納付特例制度など)
納付猶予制度は、50歳未満の方(学生を除く)で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度です。免除制度と異なり、世帯主の所得は審査対象となりません。
所得基準は全額免除と同じで、(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下となります。
学生納付特例制度
学生の方を対象とした納付猶予制度です。大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程)などに在学する学生等が対象となります。
承認基準は、学生本人の前年所得が128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下であることです。配偶者や世帯主の所得は審査対象となりません。
申請期間は年度ごと(4月から翌年3月まで)で、申請時点から2年1か月前までの期間についてさかのぼって申請できます。前年の申請によって学生納付特例が承認された方で、在学予定期間が把握できる方には、日本年金機構からハガキ形式の申請書が4月頃に送付されます。
猶予された期間の年金額への反映方法(注意点)
納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。これが免除制度との大きな違いです。
つまり、猶予を受けた期間の年金額は0円として計算されます。将来受け取る年金額を増やすためには、後述する追納制度を利用する必要があります。
ただし、猶予期間中にケガや病気で障害が残った場合の障害基礎年金や、死亡した場合の遺族基礎年金については、保険料納付済期間と同様の取り扱いとなるため、受給することができます。
申請方法と必要書類
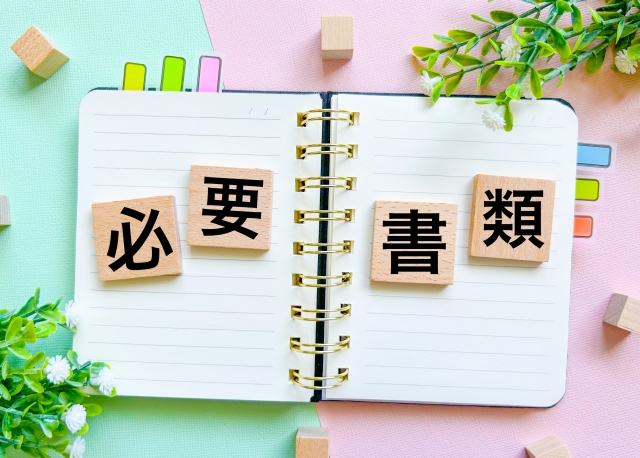
どこで申請する?(市役所、年金事務所)
申請先は以下のいずれかです。
・住民票を登録している市区役所または町村役場の国民年金担当窓口
・年金事務所
・郵送での提出も可能
また、マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルから電子申請することも可能です。24時間いつでも申請でき、記入の手間も省けるため便利です。
出典:日本年金機構
申請に必要な書類と手続きの流れ
基本的な必要書類
・基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)
・本人確認ができる証明書(運転免許証、日本国発行のパスポート、マイナンバーカード等)
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書(窓口に用意されているか、日本年金機構のホームページからダウンロード可能)
学生納付特例の場合の追加書類
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・学生証(表裏両面)のコピーまたは在学証明書(原本)
失業等による特例免除の場合の追加書類
・雇用保険受給資格者証のコピー
・雇用保険被保険者離職票のコピー
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
・その他失業の事実を確認できる書類
過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
手続きの流れ
1. 申請書に必要事項を記入
2. 必要書類を添えて市区役所または年金事務所に提出(郵送またはマイナポータルからの電子申請も可能)
3. 日本年金機構で審査(所得の申告が必要)
4. 申請から約2~3か月後に、日本年金機構から審査結果通知が郵送される
申請期間は、原則として申請月の2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます(すでに保険料が納付済の月を除く)。
申請後、審査結果が届くまでの間に納付書が届くことがありますが、これは行き違いによるものです。全額免除が承認された場合は納付書を破棄して構いませんが、審査結果が届くまでは保管しておくことをおすすめします。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
追納制度を活用しよう!免除・猶予期間を年金にフル反映させる方法

免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。追納することで、老齢基礎年金の受給額を増やすことが可能です。
追納のメリット・デメリットと期限
追納のメリット
1. 将来受け取る年金額が増える
追納した期間は、保険料を納付したときと同じ年金額で計算されます。例えば、学生納付特例で2年間納付を猶予された場合、追納しなければ年間約3,400円の減額となりますが、追納すれば満額を受け取れます。
2. 社会保険料控除による節税効果
追納した保険料は、その年の社会保険料控除として所得から控除できるため、所得税・住民税の軽減につながります。会社員の場合、通常の社会保険料とは別に年末調整での申告が必要です。
追納のデメリットと注意点
1. 期限がある
追納できる期間は、承認を受けた月から10年以内です。例えば、令和7年7月に追納する場合は、平成27年7月分以降の期間が追納できます。
2. 3年度目以降は加算額がかかる
免除・納付猶予の承認を受けた年度の翌々年度を経過してから追納する場合、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。そのため、追納する場合は早めに行う方が経済的です。
3. 追納する月は選べない
追納をする場合、納付する月は任意に選択できず、原則として最も古い月の分から順に支払っていくことになります。
追納の手続き方法
追納を希望する場合は、以下の手順で手続きを行います。
1. 「国民年金保険料追納申込書」を入手(年金事務所または日本年金機構ホームページからダウンロード)
2. 必要事項を記入し、年金事務所に郵送または直接持参
3. 申請が承認されると、日本年金機構から追納用の納付書が発行される
4. 納付書で銀行、郵便局、コンビニエンスストアなどで納付
追納用納付書は、一括払いまたは月別払いの指定ができます。ただし、クレジットカードによる追納はできません。
まとめ:もしもの時も安心!年金制度は生活を守る
国民年金の免除・猶予制度は、経済的に困難な時期を支える重要なセーフティネットです。制度の活用により、将来の年金受給権を確保しながら、現在の負担を軽減できます。
重要なポイント
・支払いが困難な場合は、未納にせず必ず免除・猶予の申請を行う
・免除期間は受給資格期間に算入され、年金額にも一定割合が反映される
・猶予期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない
・10年以内であれば追納が可能で、年金額を満額に近づけられる
・申請は市区役所、年金事務所、またはマイナポータルから電子申請が可能
年金制度は複雑に感じられるかもしれませんが、もしもの時のために用意された制度を正しく理解し、適切に活用することで、将来の安心を守ることができます。保険料の支払いが困難になった際は、早めに年金事務所や市区役所の窓口に相談し、ご自身に合った制度を利用しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



