火災保険
家財保険は必要?火災保険の家財補償の対象範囲と選び方

火災保険に加入する際、建物補償だけでなく家財保険(家財補償)を付けるべきか迷う方は多いでしょう。家具や家電など日常生活に欠かせない財産を守るために必要かどうかを判断するには、補償範囲や対象となる「家財」の内容を理解することが重要です。本記事では、火災保険における家財保険の仕組みと補償範囲を整理し、必要・不要を判断するための基準をご紹介します。
家財保険の仕組みと火災保険の「建物」との違い

火災保険には大きく分けて建物補償と家財補償があります。建物補償は、住宅そのもの(壁、屋根、床、浴室、キッチンなど)を対象とする一方、家財補償は生活に必要な動産を対象とします。
つまり、同じ火災でも「建物」と「家財」では対象が異なります。例えば火災で住宅が焼失した場合、建物補償だけでは家具や家電の買い替え費用は補償されません。家財補償を付帯することで、生活再建にかかる費用を幅広くカバーできます。
家財保険の補償対象となる「家財」の範囲

家財には、居住者が日常的に使用する動産が含まれます。主な対象例は以下の通りです。
・家具(ソファ、ベッド、タンス など)
・家電製品(テレビ、冷蔵庫、エアコン、パソコン など)
・衣類、カーテン、食器類
・貴金属、宝飾品(一定の限度額あり)
注意が必要な高額品の扱い
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品などは「明記物件」として契約時に保険会社へ申告が必要です。申告をしていない場合、これらの高額品は補償の対象外となる点に注意してください。
補償対象外となる主なもの
・自動車、バイク(原付は対象)
・現金、有価証券、預金証書
・携帯電話、スマートフォン
・建物外への持ち出し中の家財
・経年劣化や故意による損害
また、各種調査によれば、火災保険契約における家財補償の付帯率は全体でおよそ半数程度にとどまっています。特に賃貸世帯では家財補償のみを契約する例が多く、持ち家世帯では建物のみを補償対象とするケースが目立ちます。この点からも、加入状況はライフスタイルや居住形態に大きく左右されているといえます。
家財保険と地震保険の関係

火災保険(家財補償を含む)では、地震・噴火・津波による損害は補償されません。これらの災害による家財の損害に備えるには、火災保険とセットで地震保険への加入が必要です。地震保険は火災保険の30〜50%の範囲で保険金額を設定でき、家財については最大1,000万円まで補償されます。日本は地震大国であるため、地震による家財への損害リスクも考慮して検討することが重要です。
家財保険が役立つ具体的な事例
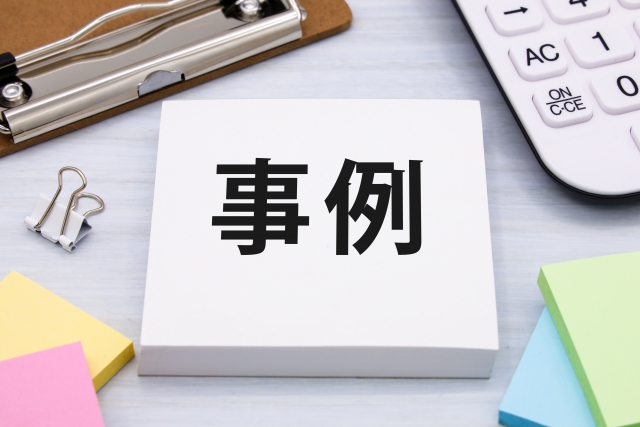
家財保険が実際にどのような場面で役立つかを具体例で確認しましょう。
・落雷による家電の故障
雷が自宅のアンテナに落ち、過電流によりテレビやパソコンが故障した場合に補償されます。
・台風や豪雨による床上浸水
床上浸水により家具・家電が水濡れで使用不能になった場合の買い替え費用が補償されます。
・給排水設備の事故による水濡れ
水道管の破裂などで家財が濡れて損害を受けた場合に補償対象となります。
・盗難による家財の盗取
空き巣により家電や貴金属が盗まれた場合、その損害額が補償されます。
家財保険が必要な人・不要な人の判断基準
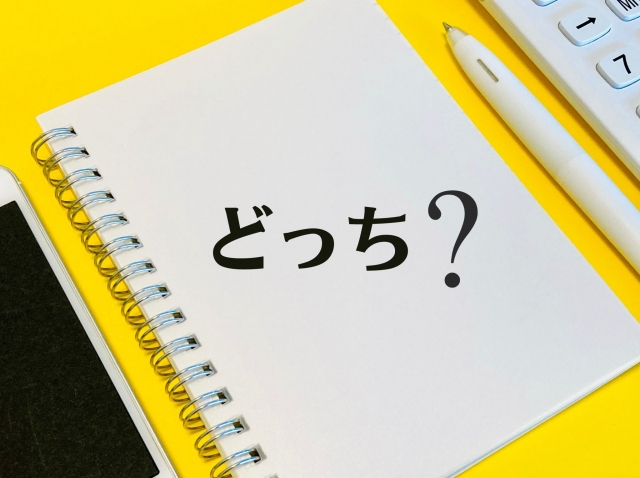
家財保険の必要性は、居住形態や所有している財産の価値によって変わります。
家財保険が必要な人
・賃貸住宅に住んでいる人(建物は大家の保険で守られるため、自分の家財を守る必要がある)
・高額な家具や家電を所有している人
・災害リスクの高い地域に居住している人
家財保険が不要な人
・所有家財が少なく、例えば合計で数十万円程度の範囲に収まる人
・十分な貯蓄があり、例えば数百万円規模の備えがあって、万一の損害を自己負担できる人
なお、実際には災害時に生活を立て直す費用が想定以上にかかるケースも多いため、慎重に検討することが望まれます。また、家財保険の保険料は家財評価額や所在地によって異なりますが、一般的には年間で数千円〜数万円程度が目安とされています。相場感を踏まえて、自分に必要な補償を無理のない範囲で選ぶことが大切です。
賃貸住宅の場合の追加ポイント
賃貸住宅では家財保険に加えて「借家人賠償責任保険」も重要です。これは借りている部屋に損害を与えた場合の修理費用を補償するもので、多くの賃貸契約で加入が求められています。
まとめ:ご自身の家財に合わせて家財保険を検討しよう
なお、家財保険は火災だけでなく、風災・水災・盗難といった幅広いリスクから家財を守ることができます。家財補償の範囲を理解し、自分のライフスタイルや所有財産の価値に応じて必要性を判断しましょう。特に賃貸世帯や家財が多い家庭では加入する意義が大きいといえます。最終的には「万一の際に生活を再建できるかどうか」を基準に、家財保険を検討することをおすすめします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



