学資保険
学資保険の返戻率は今いくら?市場別・年齢別の最新シミュレーションと注意点

ここでは、学資保険の仕組みからメリット・デメリット、現在の市場環境での注意点、さらに加入すべき人とそうでない人の特徴まで、ファイナンシャルプランナーの視点で詳しく解説します。
学資保険の基本

学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備するための貯蓄型保険です。契約者(親など)が一定期間、毎月または年単位で保険料を払い込み、満期や進学のタイミングでまとまった金額を受け取ります。多くの場合、契約者に万が一のことがあった場合には、その後の保険料払い込みが免除され、予定通りの満期金が受け取れる「保険機能」も備わっています。
一般的な特徴は以下の通りです。
・教育資金を強制的かつ計画的に貯められる
・保険と貯蓄が一体化している
・満期金や祝い金の受取時期があらかじめ決まっている
掛け金と返戻率の関係

学資保険を選ぶうえで重要なのが「返戻率」です。これは、払い込んだ保険料総額に対して、受け取る満期金の割合を示します。例えば、総支払額が200万円で満期金が210万円なら、返戻率は105%です。
返戻率は以下の要因で変動します。
・払込期間を短くすると返戻率は上がりやすい
・祝い金を複数回受け取るタイプは返戻率が低くなりやすい
・契約者の年齢や健康状態によっても変動
注意点:現在の市場環境では、一般的な返戻率は103%〜118%程度が目安です。過去に見られた120%超の商品は、マイナス金利政策の影響でほとんどなくなっています。
契約年齢や受取時期の種類
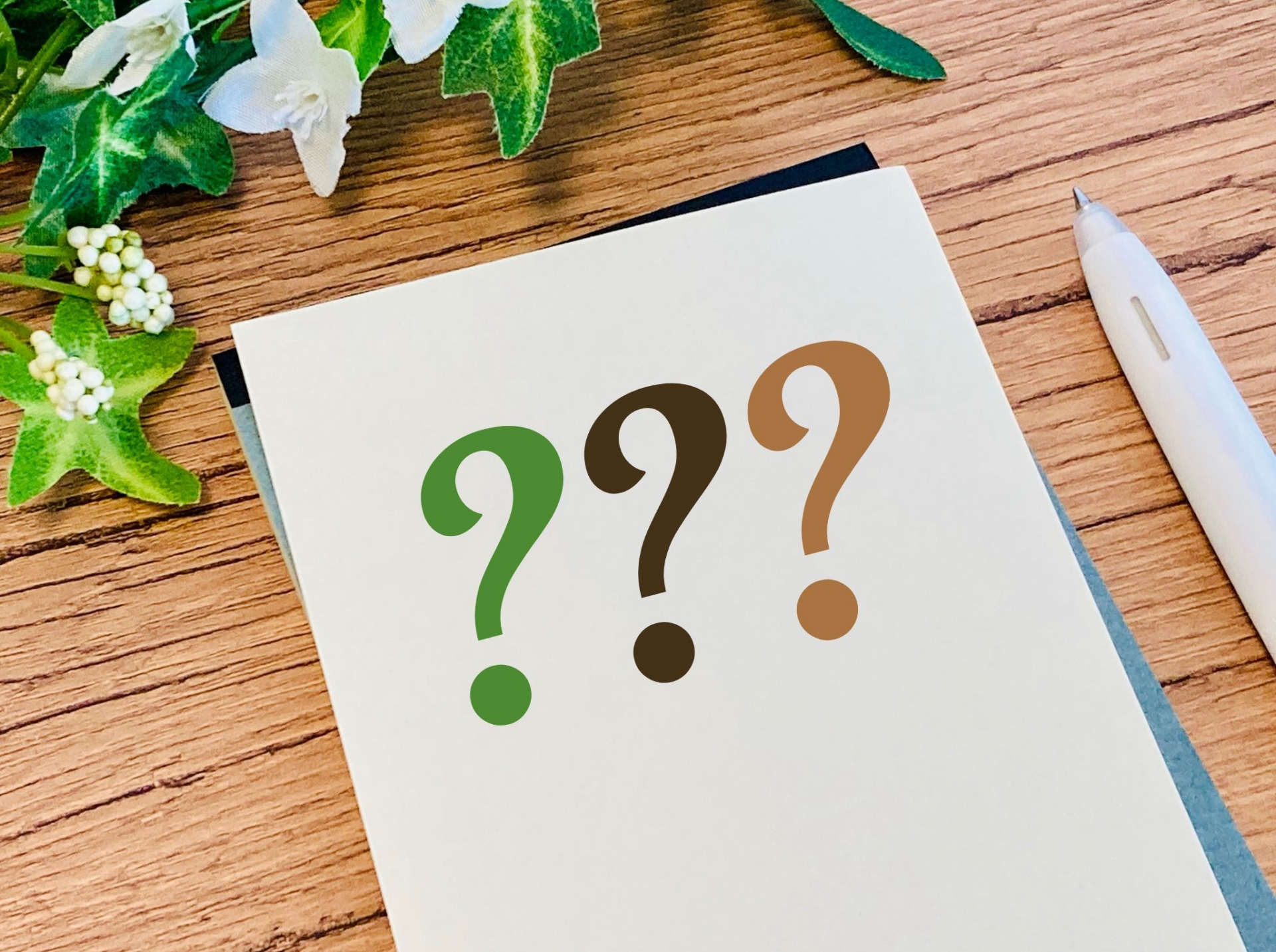
学資保険は契約時期と受取時期によってタイプが分かれます。
契約年齢の目安
・多くは0歳〜6歳までの契約が主流
・契約が早いほど返戻率が高くなりやすい
受取時期のパターン
・大学入学時に一括受取
・高校・大学入学時に分割受取
・中学・高校・大学と節目ごとに複数回受取
一括受取は運用効率が高く、分割受取は教育資金を早めに確保できるメリットがあります。教育費のピークがいつ訪れるかを想定して、受取タイミングを決めることが重要です。
年齢別返戻率シミュレーション(現実的な想定例)

以下は、現在の市場環境を踏まえた返戻率の一例です。
条件によって返戻率は大きく異なりますが、一般的な貯蓄型学資保険の返戻率は103%〜118%程度が目安です。なお、数値はあくまで例示であり、実際の契約条件や保険会社によって変わります。
・契約年齢0歳:総払込額180万円 → 満期金210万円(返戻率116.7%)
・契約年齢1歳:総払込額180万円 → 満期金207万円(返戻率115.0%)
・契約年齢3歳:総払込額180万円 → 満期金200万円(返戻率111.1%)
・契約年齢5歳:総払込額180万円 → 満期金195万円(返戻率108.3%)
契約年齢が早いほど返戻率は高くなりますが、差は年々縮小傾向にあります。
契約年齢×払込期間別シミュレーション(例)

こちらも現実的なレンジに基づいた例示です。
・0歳×5年払:満期金212万円(返戻率117.8%)
・0歳×10年払:満期金208万円(返戻率115.6%)
・0歳×15年払:満期金205万円(返戻率113.9%)
・1歳×5年払:満期金209万円(返戻率116.1%)
・3歳×5年払:満期金203万円(返戻率112.8%)
・5歳×15年払:満期金190万円(返戻率105.6%)
市場別・契約年齢別返戻率目安(2024年時点)

下記は、2024年の市場傾向を踏まえた、保険会社タイプ別・契約年齢別の返戻率目安です。
特約なし・標準的な契約条件での概算であり、実際には条件によって変動します。
・国内大手生命保険:0歳 105〜112%、1歳 104〜111%、3歳 103〜109%、5歳 102〜108%
・外資系生命保険:0歳 110〜118%、1歳 109〜117%、3歳 107〜115%、5歳 106〜114%
・共済系:0歳 103〜108%、1歳 102〜107%、3歳 101〜106%、5歳 100〜105%
・ネット専業保険会社:0歳 106〜113%、1歳 105〜112%、3歳 104〜111%、5歳 103〜110%
免責事項
本記事の返戻率は、あくまで執筆時点(2024年)の市場動向に基づいた参考値です。実際の契約における返戻率は、契約者の年齢・性別・健康状態・払込期間・受取方法・付加特約の有無・保険会社の運用実績などにより大きく変動します。契約を検討される場合は、必ず複数の保険会社・プランで見積もりを取り、最新の条件を確認してください。
現在の市場環境と返戻率低下の背景

2016年のマイナス金利政策以降、保険会社の運用利回りは低下し、学資保険の返戻率も全体的に下がっています。かつては返戻率120%超の商品も珍しくありませんでしたが、現在では特約を付けると100%を下回るケースもあるため注意が必要です。この傾向は、長期金利が上昇しない限り続く可能性があります。
元本割れリスクについて

学資保険は満期まで継続すれば元本を上回ることが多いですが、途中解約には注意が必要です。特に契約初期(1〜3年以内)で解約すると、解約返戻金は払込額を大きく下回ります。これは、保険料の一部が死亡保障や事務手数料などに充てられるためです。
したがって、契約時には長期的に払い続けられるかどうかを慎重に検討する必要があります。
加入すべき人・しなくてもよい人の違い
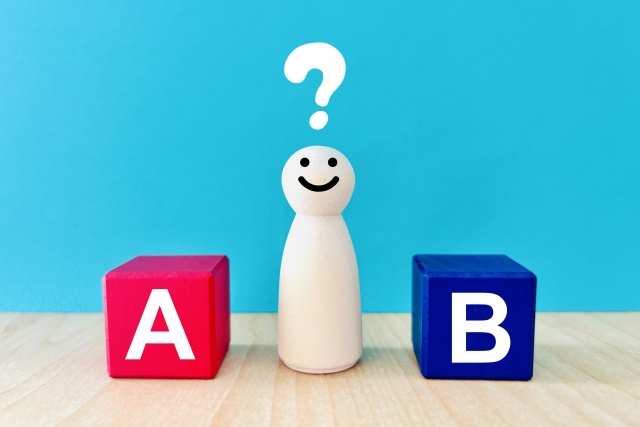
学資保険は万能ではありません。人によっては別の方法の方が合理的です。
加入をおすすめできる人
・貯蓄が苦手で計画的に積み立てられない
・契約者に万一があった場合でも教育資金を確保したい
・安定的な運用を優先し、元本割れリスクを避けたい
加入を控えてもよい人
・自分で積立や投資を継続できる自信がある
・インフレリスクに対応し、高い利回りを狙いたい
・すでに十分な教育資金の目途が立っている
まとめ
学資保険は、教育資金の確保と保険の保障機能を兼ね備えた金融商品です。しかし、低金利環境下では過去ほどの利回りは期待できず、条件によっては元本割れのリスクもあります。契約前に「返戻率」「払い込み期間」「受取時期」をシミュレーションし、家計全体のバランスを見ながら選択することが大切です。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



