公的年金制度
国民年金とは?加入義務者・保険料・受給資格期間を初心者向けに解説

すべての国民が加入する「国民年金」。しかし、その具体的な仕組みや、いくら保険料を払い、いつからいくらもらえるのか、正確に理解している人は少ないかもしれません。この記事では、国民年金の基本を、初心者にも分かりやすく解説します。
国民年金は「国民共通の基礎年金」

国民年金は、日本に住むすべての人を対象とした公的年金制度の土台となる仕組みです。老後の生活を支える老齢基礎年金だけでなく、病気やケガで障害が残ったときの障害基礎年金、一家の働き手が亡くなったときの遺族基礎年金など、生活の様々なリスクに備える役割を担っています。
国民年金の役割と加入義務者(20歳以上60歳未満の日本居住者)
国民年金への加入は義務であり、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が対象となります。国籍に関わらず、この年齢に該当すれば国民年金の被保険者として扱われるのが原則です。
具体的には、自営業者や農業従事者、学生、フリーター、無職の方など、厚生年金に加入していない方は「第1号被保険者」として、自ら保険料を納付する義務があります。一方、会社員や公務員として厚生年金に加入している方は「第2号被保険者」、その被扶養配偶者は「第3号被保険者」として、国民年金にも同時に加入している形になります。
20歳になると、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。学生であっても加入は義務ですが、所得が一定額以下の場合は学生納付特例制度を利用できる場合もあります。
国民年金保険料の仕組み

月々の保険料額とその決定方法
2025年度(令和7年度)の国民年金保険料は月額17,510円です。前年度の16,980円から530円の引き上げとなりました。この保険料額は毎年度見直されており、名目賃金の変動率に応じて改定される仕組みになっています。
国民年金の保険料は、平成16年の年金制度改正により段階的に引き上げられ、平成29年度に上限に達しました。現在は平成16年度水準で月額17,000円(保険料改定率を乗じた額)を基本とし、実質的な賃金変動に応じて毎年調整が行われています。
なお、2026年度(令和8年度)の保険料は月額17,920円となることがすでに決定されています。
保険料の納付方法(口座振替、クレジットカード、コンビニ払いなど)
国民年金保険料の納付方法には、いくつかの選択肢があります。それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
・納付書による納付
日本年金機構から毎年4月に送付される納付書を使い、金融機関やコンビニエンスストア、郵便局で現金納付する方法。手軽ですが、毎月の支払い手続きが必要となります。
・口座振替による納付
指定した金融機関の口座から自動的に引き落とされる方法。納付忘れの心配がなく、前納制度を利用すると最も割引額が大きくなります。
・クレジットカードによる納付
クレジットカードで自動的に納付する方法です。カードのポイントが貯まるメリットがありますが、割引額は納付書と同じになります。
・スマートフォン決済アプリによる納付
スマートフォンのカメラ機能で納付書のバーコードを読み取り、決済アプリを通じて納付する方法。2023年2月から利用可能になりました。
前納割引を活用した保険料節約術
国民年金には、一定期間分の保険料をまとめて前払いすることで割引を受けられる「前納制度」があります。前納期間が長いほど、また口座振替を利用するほど割引額が大きくなります。
2025年度における前納割引の具体例は以下の通りです。
・6ヶ月前納(4月~9月分または10月~3月分)
口座振替:103,870円(1,190円の割引)
現金・クレジットカード:104,210円(850円の割引)
・1年前納(4月~翌年3月分)
口座振替:205,720円(4,400円の割引)
現金・クレジットカード:206,390円(3,730円の割引)
・2年前納(4月~翌々年3月分)
口座振替:408,150円(17,010円の割引)
現金・クレジットカード:409,490円(15,670円の割引)
最も割引率が高いのは口座振替による2年前納で、約4%の割引となります。経済的な余裕がある方は、この制度を積極的に活用することで保険料を節約できます。ただし、前納期間中に厚生年金に加入した場合は、未経過期間分の保険料が返金されますので安心です。
前納を希望する場合、2年前納・1年前納・6ヶ月前納(4月開始分)は2月末までに、6ヶ月前納(10月開始分)は8月末までに年金事務所または市区町村役場で手続きが必要です。
国民年金の「受給資格期間」とは?
原則10年以上の納付が必要な理由
国民年金から老齢基礎年金を受け取るためには、保険料を納付した期間や免除された期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上必要です。これは平成29年8月1日に改正されたもので、それ以前は原則25年以上必要でした。
この受給資格期間の短縮により、これまで年金を受け取れなかった多くの人が年金受給の権利を得られるようになりました。ただし、受給資格期間を満たしても、実際に納付した期間が短ければ、それに応じて年金額は減額されます。
満額の老齢基礎年金を受け取るためには、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、保険料を納付する必要があります。2025年度の老齢基礎年金の満額は月額69,308円(年額831,696円)です。
免除・猶予期間、合算対象期間(カラ期間)の考え方
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合、未納のまま放置するのではなく、免除や猶予の制度を利用することが重要です。
・保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除されます。免除期間は受給資格期間に算入され、年金額にも一定割合が反映されます。
・納付猶予制度
50歳未満の方を対象に、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。猶予期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。ただし、10年以内であれば追納することで年金額を増やすことができます。
・学生納付特例制度
学生で本人の所得が一定額以下の場合、在学中の保険料納付が猶予されます。こちらも受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されないため、可能であれば追納することが推奨されます。
・合算対象期間(カラ期間)
過去に任意加入できる期間に加入しなかった期間などが該当し、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。海外居住期間や厚生年金加入者の配偶者だった期間などが該当する場合があります。
これらの期間を適切に活用することで、受給資格期間を満たし、将来の年金受給権を確保することができます。
国民年金で受け取れる主な年金
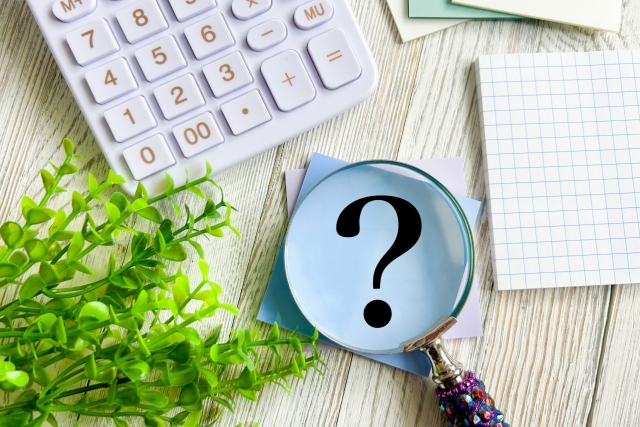
国民年金からは、生活の様々な局面に応じて3種類の給付が行われます。
老齢基礎年金
65歳から受け取れる年金で、国民年金の中核となる給付です。受給資格期間を10年以上満たし、保険料を40年間納付した場合、2025年度は月額69,308円の満額を受け取ることができます。
納付期間が40年に満たない場合や、免除期間がある場合は、その分に応じて減額されます。また、60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給することも、66歳以降に繰下げ受給することも可能で、それぞれ年金額が調整されます。
第1号被保険者の場合、月額400円の付加保険料を上乗せして納付すると、老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」が加算される付加年金制度も利用できます。
障害基礎年金
病気やケガによって一定の障害状態になった場合に支給される年金です。障害の程度に応じて1級と2級に分かれており、現役世代でも受給できる重要な保障制度となっています。
障害基礎年金を受給するには、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金の被保険者であることや、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
障害等級1級の場合は老齢基礎年金満額の1.25倍、2級の場合は満額と同額が支給されます。また、生計を維持している18歳到達年度末までの子(または20歳未満で障害等級1・2級の子)がいる場合は、子の加算額も支給されます。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。
ここでいう「子」とは、18歳到達年度末までの子または20歳未満で障害等級1・2級に該当する子を指します。遺族基礎年金の額は、基本額に子の人数に応じた加算額が加わります。
遺族基礎年金を受給するには、死亡した人が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。この制度により、万が一の際にも残された家族の生活が一定程度保障される仕組みになっています。
国民年金を確実に納めることの重要性

国民年金の保険料を納めることは、単なる義務ではなく、自分と家族の将来を守るための重要な備えです。保険料を未納のまま放置すると、以下のようなリスクがあります。
・老後の年金が受け取れない、または減額される
受給資格期間を満たせなければ老齢基礎年金は受け取れません。また、納付期間が短いほど年金額も少なくなります。
・障害年金や遺族年金が受け取れない場合がある
一定の保険料納付要件を満たしていないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができません。若いうちに障害を負ったり、一家の働き手が亡くなったりした場合、その保障が得られない可能性があります。
・財産差押えのリスク
正当な理由なく保険料を滞納し続けると、最終的には財産の差押えが行われる場合があります。
経済的に保険料の納付が困難な場合は、未納にせず必ず免除・猶予制度の申請を行いましょう。これらの制度を利用することで、受給資格期間に算入され、将来の年金受給権を確保することができます。
また、保険料には2年の納付期限があります。納付期限を過ぎると時効により納付できなくなるため、できるだけ早めに対応することが大切です。
まとめ:国民年金が支えるあなたの老後と万一の備え
国民年金は、すべての国民に共通する基礎年金として、老後の生活保障だけでなく、障害や死亡といった予期せぬリスクにも対応する総合的な社会保障制度です。
2025年度の保険料は月額17,510円ですが、前納制度を活用することで割引を受けることができます。特に口座振替による2年前納を利用すれば、17,010円もの割引が適用されます。
老齢基礎年金を受け取るには10年以上の受給資格期間が必要ですが、満額を受け取るためには40年間の納付が必要です。経済的に困難な場合は、免除・猶予制度を必ず利用しましょう。
20歳になったら国民年金への加入は義務です。学生であっても例外ではありません。自分の将来と家族の生活を守るため、国民年金の保険料は確実に納付し、将来に備えることが重要です。
詳しい手続きや相談については、お近くの年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口、あるいは日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



