公的年金制度
厚生年金とは?加入対象者、保険料の計算、受給要件を会社員・公務員向けに詳説

会社員や公務員が加入する「厚生年金」は、国民年金に上乗せされる2階部分の年金として、老後の生活を支える重要な制度です。保険料の計算方法や将来受け取る年金額への影響は複雑に見えますが、基本的な仕組みを理解すれば、自分の年金について適切に把握できるようになります。この記事では、厚生年金について、働く人々に役立つ情報を詳しく解説していきます。
厚生年金は「働く人のための年金」:国民年金の上乗せ部分
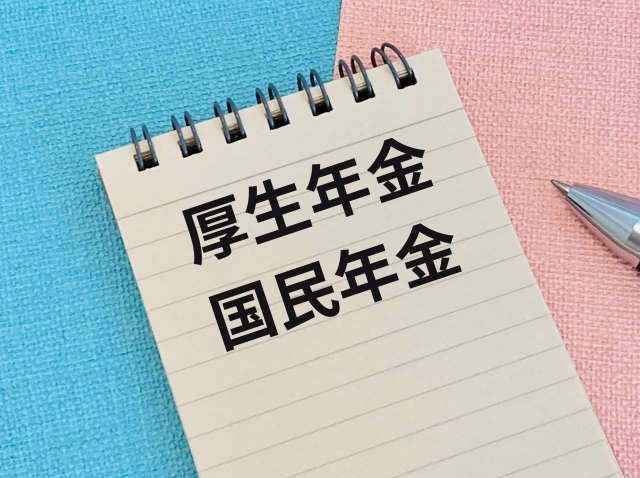
日本の公的年金制度は、よく「2階建て構造」と表現されます。1階部分は20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する国民年金(基礎年金)、2階部分は会社員や公務員が加入する厚生年金となっています。厚生年金に加入すると、自動的に国民年金にも加入することになり、将来は国民年金と厚生年金の両方を受け取れるのが大きな特徴です。
厚生年金の役割と加入対象者
厚生年金は、病気やけが、高齢などの理由で働けなくなったり、被保険者が亡くなって遺族が困窮したりする状況を救済するために設けられた制度です。昭和17年に工場勤務などの男性労働者を対象に労働者年金として発足し、昭和19年には厚生年金保険法と名称を改め、事務職員や女性労働者にも範囲を広げました。
厚生年金の加入対象者は、適用事業所に勤める70歳未満の会社員・公務員などです。適用事業所とは、法人事業所(株式会社や有限会社など)のほか、常時5人以上の従業員がいる個人事業所(一部業種を除く)を指します。年齢の下限は設けられていないため、就職と同時に厚生年金に加入し、70歳になると資格を失うという仕組みになっています。
厚生年金加入者は、国民年金では第2号被保険者として扱われます。第2号被保険者の配偶者で一定の要件を満たす人は第3号被保険者となり、自身で保険料を納付する必要がありません
厚生年金保険料の計算方法

厚生年金の保険料は、毎月の給与や賞与に応じて計算されます。この計算の基礎となるのが「標準報酬月額」と「標準賞与額」という概念です。
標準報酬月額とは?給与明細の「等級」を確認しよう
標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の幅で区切り、その区分ごとに定められた金額のことです。これは保険料の計算を簡略化するために用いられる指標で、2025年11月現在、1等級(88,000円)から32等級(650,000円)までの32段階に区分されています。
標準報酬月額の対象となる報酬には、基本給だけでなく、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、住宅手当、物価手当など各種手当が含まれます。年4回以上支給される賞与や、現物で支給される食券、社宅、独身寮なども報酬に含まれるため注意が必要です。
標準報酬月額は通常、毎年7月1日に算出されます。算出の根拠となるのは、その年の4月から6月の3ヵ月間の給与の月平均額です。この期間の平均額を計算し、それを標準報酬月額表の区分にあてはめることで等級が決まります。この手続きを「定時決定」といい、決定された標準報酬月額は原則として、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
例えば、4月の給与が31万円、5月の給与が27万円、6月の給与が32万円の場合、平均額は30万円となります。これを標準報酬月額表にあてはめると、報酬月額29万円から31万円のゾーンに含まれるため、第19等級(標準報酬月額30万円)と決定されるのです。
なお、給与が大きく変動した場合には「随時改定」が行われます。給与の3ヵ月平均で2等級以上の差が生じるような変動があった場合、標準報酬月額の修正が行われます。
標準報酬月額の上限引き上げについて
2025年6月に成立した年金制度改正法により、厚生年金の保険料計算の基準となる標準報酬月額の上限が、現行の65万円から75万円へ段階的に引き上げられることが決まりました。具体的には、以下のスケジュールで実施される予定です。
・2027年9月:65万円→68万円(第33等級新設)
・2028年9月:68万円→71万円(第34等級新設)
・2029年9月:71万円→75万円(第35等級新設)
この改定により、高所得者はこれまでより多くの保険料を納めることになりますが、その分、将来の年金受給額も増加します。標準報酬月額の上限引き上げは、収入に応じた負担(応能負担)の強化と、所得再分配機能の強化を目的としています。
賞与からの保険料計算(標準賞与額)
賞与に対する保険料は、標準賞与額に基づいて計算されます。標準賞与額とは、税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回につき150万円が上限です。計算の結果、150万円を超える場合は150万円として計算されます。
厚生年金保険料は標準賞与額に保険料率18.3%を乗じて計算し、労使折半で負担します。なお、同じ月に複数回賞与が支給される場合は合算して計算されます。
労使折半の仕組みと、あなたの負担額
厚生年金の保険料は、事業主(会社)と被保険者(従業員)が半分ずつ負担する「労使折半」という仕組みになっています。保険料率は全額で18.3%と定められており、平成29年を最後に引き上げが終了し、現在は固定されています。
例えば、標準報酬月額が30万円の人の場合、厚生年金保険料は以下のように計算されます。
・保険料全額:30万円×18.3%=54,900円
・従業員本人の負担額:27,450円
・企業の負担額:27,450円
標準賞与額が上限の150万円の場合、賞与にかかる保険料は274,500円(150万円×18.3%)となり、企業と従業員がそれぞれ137,250円を負担することになります。
保険料は毎月の給与と賞与から控除され、事業主が控除した被保険者の保険料に事業主負担分を併せて、翌月末までに日本年金機構に納めます。
厚生年金保険料が将来の年金額に与える影響

厚生年金で将来受け取る年金額は、現役時代に納めた保険料、つまり報酬と加入期間に基づいて計算されます。保険料を納めた期間が長いほど、また報酬が高いほど、老後に受け取る年金額も多くなる仕組みです。
報酬比例部分の計算基礎(平均標準報酬月額・平均標準報酬額)
老齢厚生年金の額を決定する中核となるのが「報酬比例部分」です。厚生年金加入期間中の報酬とその加入期間に基づいて年金額が計算される部分で、以下のような計算式で求められます。
報酬比例部分=
(平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月までの加入期間の月数)+
(平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入期間の月数)
ここで、平均標準報酬月額とは2003年3月以前の厚生年金加入期間における標準報酬月額の平均値を指します。一方、平均標準報酬額は2003年4月以降の厚生年金加入期間における標準報酬月額と標準賞与額の総額を加入期間の月数で割ったものです。
この計算式からわかるように、現役時代の報酬が高いほど、また加入期間が長いほど、報酬比例部分の金額が大きくなり、将来受け取る年金額が増える仕組みとなっています。
ボーナスが年金額にどう影響するか
2003年4月の制度改正により、賞与も厚生年金の保険料計算の対象となりました。これにより、賞与からも保険料を納めることになりましたが、その分、将来受け取る年金額の計算にも賞与が反映されるようになりました。
平均標準報酬額の計算には、月々の標準報酬月額だけでなく、標準賞与額も含まれます。そのため、賞与が多い人ほど、平均標準報酬額が高くなり、結果として報酬比例部分の年金額も増加します。ボーナスは単に現役時代の収入を増やすだけでなく、老後の年金額にも直接影響を与える重要な要素なのです。
厚生年金で受け取れる主な年金

厚生年金制度では、老齢、障害、死亡という三つの事由に対して、それぞれ年金給付が用意されています。
老齢厚生年金
老齢厚生年金は、原則として65歳から受給できる年金です。現役時代に保険料を納めた期間や賃金に応じて受給額が決まります。受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること
・厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること
出典:日本年金機構「老齢年金(受給要件・支給開始時期・年金額)」
老齢厚生年金は、前述の報酬比例部分を基礎として計算されます。65歳以降の年金額は、報酬比例部分に経過的加算と加給年金額を加えた金額となります。
なお、厚生年金には70歳まで加入できます。厚生年金の加入期間が長くなれば、その分老齢厚生年金を増やすことが可能です。65歳から受け取る年金額では生活費が足りなくなるようであれば、厚生年金に加入して長く働くことを考えるのも一つの選択肢でしょう。
また、老齢厚生年金には「繰下げ受給」の制度があります。65歳以降に受給開始を遅らせることで、年金額を最大84%(75歳まで繰下げた場合)増額できます。増額率は、65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数に0.7%を乗じて計算されます。
障害厚生年金
障害厚生年金は、病気やケガが原因で厚生年金の被保険者本人が障害認定を受けた場合に受給できる年金です。障害厚生年金には、障害等級1級から3級までの年金があります。
・障害等級1級:報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金額
・障害等級2級:報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金額
・障害等級3級:報酬比例部分の年金額
出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」
1級または2級の場合、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるとき、配偶者加給年金が加算されます。また、1級と2級の場合は、国民年金の障害基礎年金もあわせて支給されます。3級は報酬比例部分のみの支給となりますが、加入期間が短いなどの理由で極端に金額が低くならないよう、最低保障額が設けられています。
なお、厚生年金保険の被保険者が障害認定を受けた場合、被保険者期間が300月未満であれば300月とみなして計算されます。これは、若い時期に障害を負った人でも一定の年金額が保障されるようにするための措置です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、生計を維持されていた遺族に支給される年金です。遺族厚生年金を受給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、上位順位者が受給できます。
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額×3/4で計算されます。厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、被保険者期間が300月未満であれば300月とみなして計算されます。
出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
なお、遺族厚生年金については、2025年6月に成立した年金制度改正法により、2028年4月から大幅な見直しが予定されています。特に重要な変更として、60歳未満で配偶者と死別した場合、18歳年度末までの子どもがいない場合は、男女共通で原則5年の有期給付となります。ただし、給付期間が短縮される代わりに、5年間の給付額は現在の約1.3倍に増額される予定です。
また、5年間の有期給付の終了後も、障害状態にある人や収入が十分でない人については、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できる継続給付の仕組みが設けられます。さらに、65歳以降の生活保障として、「死亡分割」という新しい制度が導入され、亡くなった配偶者の厚生年金加入記録の一部(約半分)を、残された配偶者の年金記録に上乗せできるようになります。
厚生年金を理解して、働き方と年金受給を最適化する
厚生年金の仕組みを理解することは、将来の生活設計を考える上で非常に重要です。標準報酬月額の決定時期である4月から6月の報酬が将来の年金額に影響を与えることを知っていれば、残業の調整など働き方について考える際の参考になるでしょう。
また、賞与も年金額の計算に含まれることを理解すれば、総合的な報酬の在り方について、より深く検討できるようになります。厚生年金は、単に保険料を納めるだけの制度ではなく、将来の安定した生活を支える重要な資産形成の仕組みなのです。
さらに、厚生年金の加入期間が長くなれば年金額が増えることを考慮すると、65歳以降も働き続けるという選択肢も視野に入ってきます。ただし、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる可能性があるため、繰下げ受給などと組み合わせた戦略的な検討が必要になります。
厚生年金制度は、今後も社会経済の変化に応じて見直しが続けられていくでしょう。標準報酬月額の上限引き上げや、遺族厚生年金の見直しなど、重要な改正が予定されています。こうした制度改正の動向にも注意を払いながら、自分に最適な働き方と年金受給の方法を考えていくことが大切です。
まとめ:あなたの働きが直結する厚生年金の恩恵
厚生年金は、会社員や公務員にとって、国民年金に上乗せして将来の生活を支える重要な制度です。現役時代に納める保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に基づいて計算され、保険料率18.3%を労使折半で負担します。
将来受け取る年金額は、報酬比例部分を基礎として計算されるため、現役時代の報酬が高く、加入期間が長いほど年金額も増加します。老齢厚生年金だけでなく、障害厚生年金や遺族厚生年金といった保障も用意されており、万が一の際にも生活を支える仕組みとなっています。
標準報酬月額の上限引き上げや遺族厚生年金の見直しなど、制度改正も予定されています。こうした変化に注意を払いながら、自分の働き方と年金受給について適切に理解し、将来に向けた計画を立てることが重要です。厚生年金制度を正しく理解し、働き方と年金受給を最適化することで、より安心した老後を迎えることができるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



