医療保険
医療保険の告知書、どう書けばいい?記入方法と注意点を徹底解説

医療保険に加入する際、必ず記入が求められるのが「告知書」です。これは、ご自身の健康状態や病歴を保険会社に伝えるための重要な書類ですが、「どこまで詳しく書けばいいのか」「過去の通院歴は全部書く必要があるのか」と、記入方法に悩む方も多いでしょう。
この記事では、医療保険の告知書の正しい記入方法と注意点を解説します。告知書に記載する主な内容、告知義務違反が招く重大なリスク、そして嘘をつかずに正直に記入することの重要性まで。後悔しないための賢い保険選びのヒントを提案します。
告知書とは?記入する主な内容

告知書とは、保険会社が加入希望者の健康状態を把握し、リスクに応じた保険料や保障内容を決定するための重要な書類です。
告知書に記入する主な内容
現在の健康状態:
現在治療中の病気や、最近受けた手術の有無。
過去の病歴:
過去に診断された病気や、入院・手術の有無。
現在の職業:
危険を伴う職業に就いていないか。
身長・体重:
BMI(肥満度)の計算に利用されます。
喫煙の有無:
過去の喫煙歴は、がんや心疾患のリスクを判断する上で重要な情報です。
告知書を記入する際の注意点
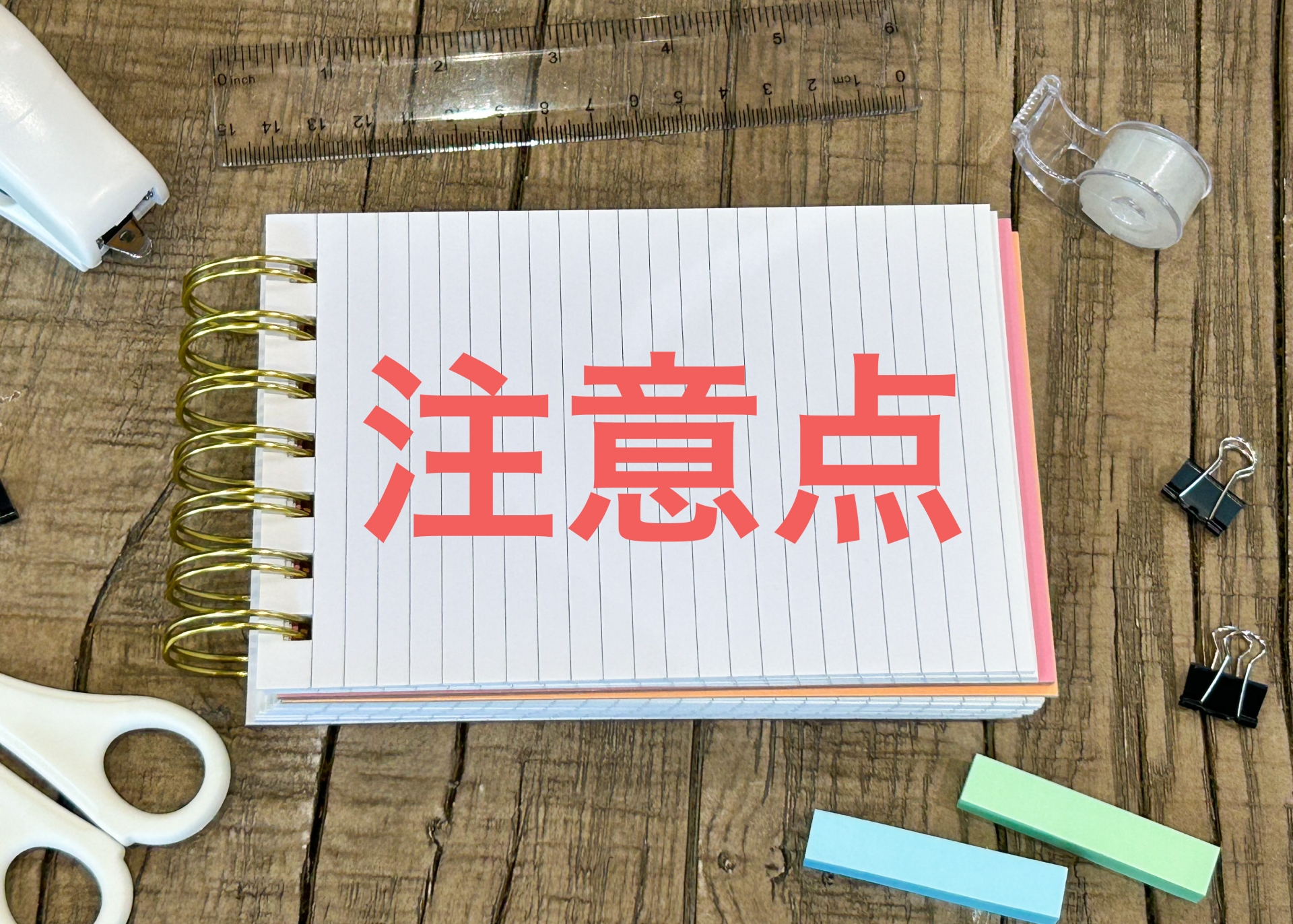
告知書は、ご自身の健康状態を正確に伝えるためのものです。以下の点に注意して、慎重に記入しましょう。
告知事項を正直に伝える
告知義務違反のリスク:
・告知書に事実と異なることを記載した場合、告知義務違反となります。
・「うっかり忘れ」や記入漏れであっても、告知義務違反と判断される可能性があるため、注意が必要です。
正直に伝える:
症状が軽い場合でも、医師の診察や投薬を受けている場合は、その事実を正直に伝えましょう。例えば、軽い病気で投薬を受けているにも関わらず、「保険の営業がせっかく来てくれたのだから・・」と、投薬の事実を隠して、告知書に書かないということも「アウト」です。最終的に、自分も担当営業もどちらも不幸になりますので、正直に伝えるよう、心がけてください。
健康診断の結果を参照する
記憶が曖昧な場合:
・過去の治療歴や健康診断の結果は、記憶が曖昧になりがちです。
・健康診断の結果や、病院の領収書、お薬手帳などを参照して、正確な情報を記入しましょう。
診断書は不要:
告知書は、ご自身で記入するものであり、診断書を添付する必要はありません。
告知義務違反が招く重大なリスク

告知義務違反は、保険契約者にとって重大なリスクを招きます。
契約が解除される
保険会社による契約解除:
・告知義務違反が発覚した場合、保険会社は契約を解除することができます。
・保険法では、責任開始日から5年を経過した場合は解除できないと規定されていますが、多くの保険会社は、約款で「責任開始日から2年を超えて有効に継続したときは解除できない」と緩和しています。
保険料の返還:
・告知義務違反が原因で契約が解除された場合、解約返戻金がある保険契約の場合は、その分が払い戻されることがあります。
・しかし、悪質な告知義務違反は、詐欺による契約の取り消しとみなされる場合があります。この場合、2年経過後でも契約が取り消され、保険料は返還されません。
保険金・給付金が支払われない
給付金の不払い:
告知義務違反が原因で、いざという時に保険金や給付金が支払われない可能性があります。
まとめ:正直な告知が、いざという時の安心につながる
医療保険の告知書は、ご自身の健康状態を正確に伝えるための、最も重要な手続きの一つです。
・告知書に記載する内容を正しく理解し、正直に、ありのままを記入しましょう。
・告知義務違反は、契約の解除や保険金不払いといった重大なリスクを招きます。
・少しでも不安な点があれば、保険会社の担当者に正直に相談しましょう。
ここで解説した知識を活用して、告知書を適切に作成し、満足のいく保険を選択しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



