就業不能保険
免責期間と給付条件で選ぶ就業不能保険|早く受け取れるタイプの特徴と注意点

本記事では、免責期間の基礎知識から短期免責の利点・欠点、保険料の影響、そして選び方のポイントまで、独立系FPの視点から詳しく解説します。
免責期間とは?
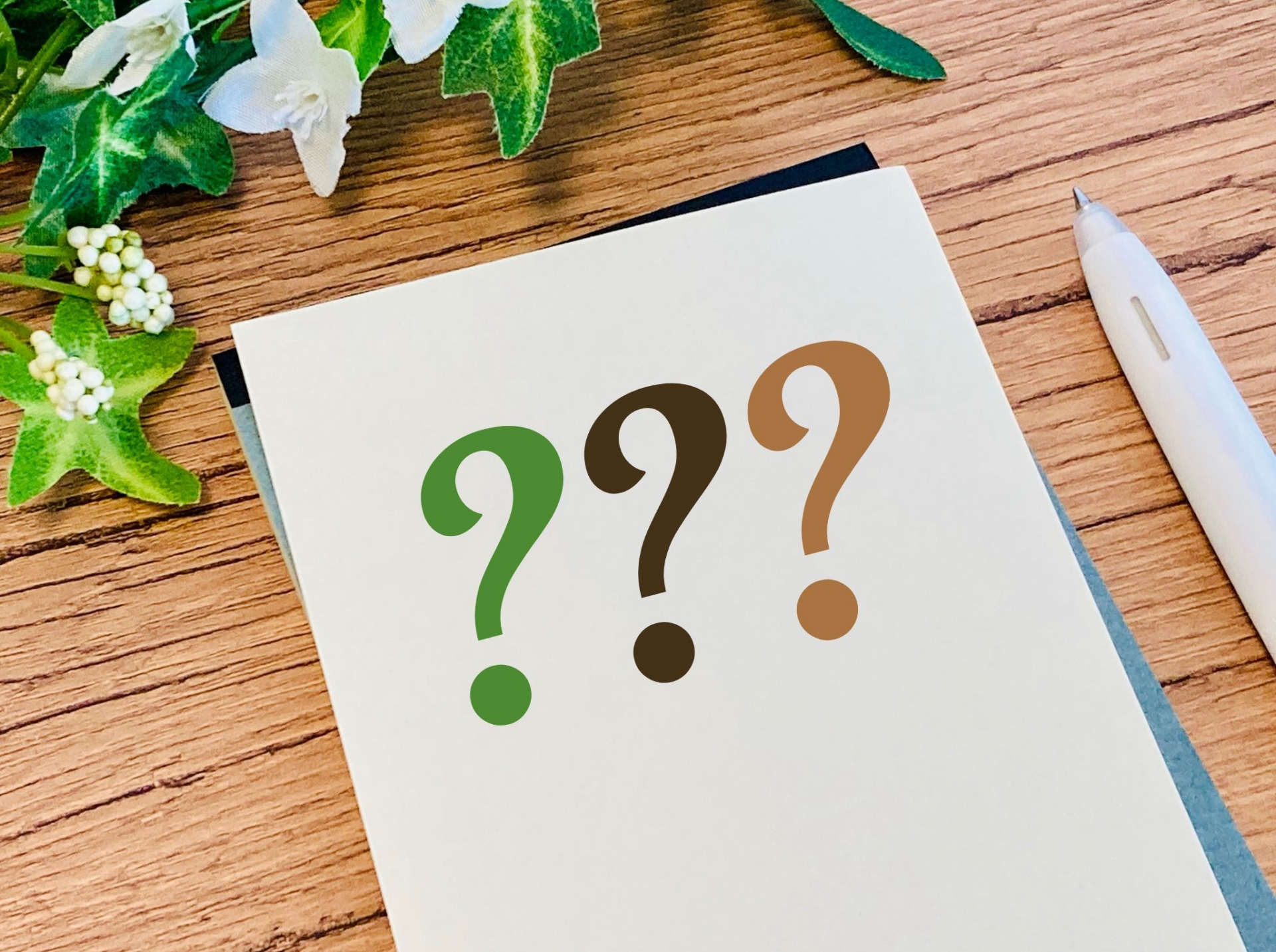
免責期間とは、就業不能状態になってから保険金が支払われるまでの「待機期間」を指します。例えば「免責期間60日」とは、就業不能状態が60日以上継続した場合に、61日目から保険金が支払われる仕組みです。
就業不能保険では、免責期間が60日・90日・180日のいずれかに設定されることが一般的です。一方で、所得補償保険の場合は免責期間が短く、7日や14日などの設定が可能なケースもあります。免責期間の短さを優先する場合、この違いを理解しておくことが重要です。
短期免責のメリット・デメリット

メリットとしては、給付開始までの期間が短いため、貯蓄や生活費への影響を抑えやすくなる点が挙げられます。例えば、貯蓄額が少ない世帯や、自営業で休業時の公的補償が乏しい方にとっては大きな安心材料です。
一方でデメリットとしては、免責期間が短いほど保険料が割高になりやすく、加入条件も厳しくなる傾向があります。また、就業不能保険の場合、極端に短い免責期間(例:30日未満)はほとんど存在しないため、短期免責を求める場合は所得補償保険の検討も必要になります。
免責期間別の特徴

免責期間ごとの一般的な特徴は以下の通りです(就業不能保険の場合):
・60日:比較的早く給付開始、保険料はやや高め
・90日:給付までの待機期間と保険料のバランスが良い
・180日:保険料は安いが、半年間は自己負担
なお、所得補償保険では「7日免責」「14日免責」なども存在し、短期休業にも対応できます。ただし、こちらは長期的な就業不能よりも短〜中期の所得補填に向いた保険です。
保険料への影響

免責期間が短くなるほど、保険会社の負担リスクが増すため、保険料は高くなる傾向にあります。一次情報(日本FP協会の解説)でも、短期免責は割高になる旨が説明されています。一般的には、90日免責と比べて60日免責にすると保険料が上昇する傾向があります。
また、所得補償保険で免責期間を7日から14日に延ばすだけで、年間保険料が下がるケースもあります。このため、短期免責を希望する場合でも、必要な生活保障額と保険料負担のバランスをしっかり試算することが重要です。
短期免責プランの事例

就業不能保険の短期免責プランの例としては、「免責期間60日」が最短のことが多く、30日以下は稀です。一方、所得補償保険では7日や14日免責が一般的に提供されています。
例えば、Aさん(会社員)が60日免責の就業不能保険に加入した場合、2か月間は貯蓄で生活を維持し、その後から毎月の給付金を受け取る形となります。Bさん(自営業)が7日免責の所得補償保険を選んだ場合は、短期間の休業でも早期に補償が始まり、固定費の支払いに充てやすくなります。
FPによるケース別シミュレーション

免責期間と給付条件の選び方は、職業や家計の状況によって大きく異なります。ここでは、3つのケースでシミュレーションしてみましょう。
ケース1:会社員(公的保障あり)
・年収:500万円、貯蓄:200万円、傷病手当金あり
→ 会社員は健康保険から傷病手当金が支給されます。
2022年1月からの制度改正により、支給期間は「最長1年6か月」である点は変わりませんが、支給期間が通算化され、復職と再休業を繰り返した場合でも、同一の傷病について通算1年6か月まで受給可能となりました。そのため、免責期間90日でも十分に対応でき、保険料を抑えつつ長期保障を確保できます。
ケース2:自営業(公的保障なし)
・年収:500万円、貯蓄:100万円、公的傷病手当なし
→ 休業時の公的補償がないため、免責期間60日を選択することで早期に給付が始まる設計が望ましい。場合によっては所得補償保険と組み合わせ、短期休業にも対応できるようにする。
ケース3:共働き世帯(固定費が高い)
・世帯年収:800万円、貯蓄:300万円、住宅ローン返済あり
→ 一方の収入が途絶えても、もう一方の収入である程度補えるが、住宅ローンや教育費など固定費が高いため、免責期間90日+十分な給付額を設定し、生活レベルを維持できる設計が望ましい。
選び方のポイント

FPの視点から見ると、免責期間の選び方は次の基準で考えると良いでしょう。
・生活費を何か月分備えているか(貯蓄額)
・公的保障(傷病手当金など)の有無
・長期の保障を重視するか、短期の補償を重視するか
・就業不能保険と所得補償保険の違いを理解して選択する
まとめ
免責期間が短い保険は、経済的リスクを早期に軽減できるメリットがありますが、保険料や加入条件にも影響します。特に就業不能保険では60日が最短であることが多く、30日未満はほとんど見られません。もし7日や14日などの極端に短い免責を希望する場合は、就業不能保険ではなく所得補償保険を検討するのが現実的です。
最終的には、生活費の備え・公的保障・必要保障期間を総合的に考慮し、自分に合った免責期間を設定することが大切です。
免責期間×給付条件の選び方チェックリスト
以下のチェックリストに答えることで、自分に合った免責期間と給付条件の方向性が見えてきます。
・生活費の備えは何か月分ありますか?(3か月未満 → 短めの免責を検討)
・公的保障(傷病手当金や労災保険給付)はありますか?(なし → 短めの免責を検討)
・休業時の家計支出の中で、固定費はどれくらいありますか?(多い → 給付額を多めに設定)
・職業上、休業リスクは高いですか?(高い → 短期免責や補償額の上乗せを検討)
・長期的な就業不能と短期的な休業、どちらを主に備えたいですか?(短期 → 所得補償保険も候補)
・保険料負担は毎月どの程度まで許容できますか?(高額不可 → 免責期間を長めに設定)
このチェックを踏まえて、免責期間と給付条件をバランスよく決定することが、無理なく続けられる保障設計のポイントです。
参考情報
日本FP協会「働けないときの収入ダウンに備えた民間保険の活用法」
厚生労働省:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



