ニーサ
個人年金保険vsつみたて投資枠!老後資金の貯め方を比較【2025年版】

ここでは、現在の新NISA制度のつみたて投資枠と、老後資金準備の定番である個人年金保険を比較し、特徴・メリット・デメリット、両者を組み合わせた場合の資産シミュレーション、さらに年代別おすすめ配分例や行動ステップまで解説します。
つみたて投資枠の仕組みと非課税メリット

つみたて投資枠は、新NISA制度の一部で、金融庁が認めた長期・積立・分散投資向けの投資信託やETFに投資できる制度です。最大の魅力は、運用益が非課税になること。通常、投資で得た利益には20.315%の税金がかかりますが、この制度では税負担がゼロになります。
・年間投資上限額:120万円(非課税保有限度額は全体で1,800万円まで)
・投資対象:低コストで長期運用に適した投資信託・ETF
・非課税期間:無期限(売却→再投資も可能)
【20年間・年4%・月3万円積立の例】
・課税口座:約1,022.8万円
・つみたて投資枠:約1,100万円 → 税金の有無で約77.2万円の差
金融庁 つみたてシミュレーターを使って算出 税率は20.315%としています。
個人年金保険の仕組みと返戻率

個人年金保険は、保険会社に一定期間保険料を積み立て、将来年金形式で受け取る仕組みです。契約時に受取額が確定し、運用リスクを避けられます。また、生命保険料控除のうち個人年金保険料控除の対象となり、節税効果があります。
返戻率は契約条件によりますが、現在の低金利環境では102〜105%程度が一般的です(変額型・外貨建てなど一部例外あり)。
・積立期間:10〜30年程度
・受取方法:確定年金・終身年金など
・節税効果:控除額は所得税最大4万円、住民税最大2.8万円(軽減額は所得税率によって変動)
注意点として、途中解約すると元本割れリスクが高く、資金の流動性は低い点があります。
運用効率と保障の有無
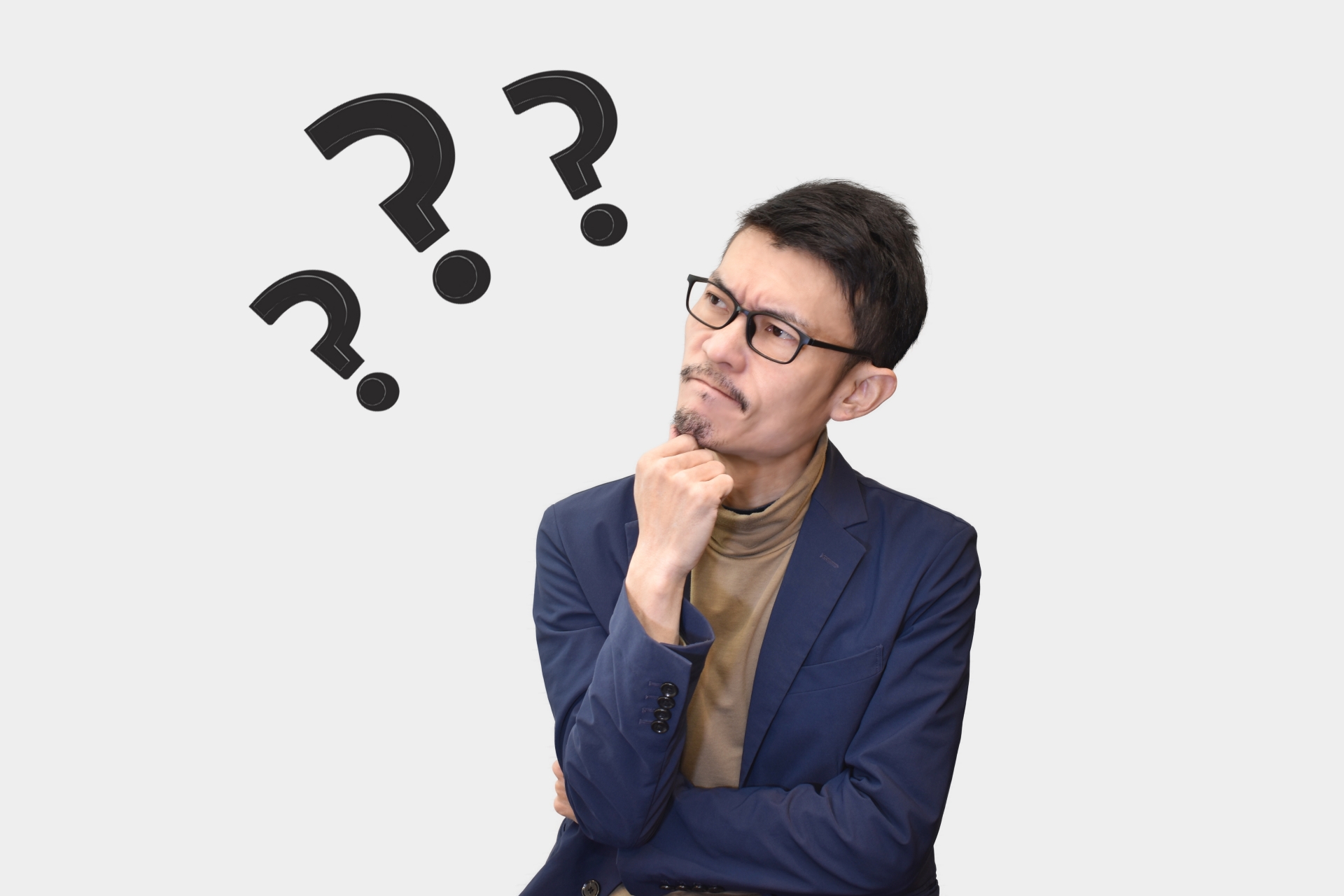
つみたて投資枠:市場連動で利回り3〜5%が期待できる。元本保証はないが、非課税と複利効果で成長性が高い。
個人年金保険:利回りは低いが受取額が確定し、節税効果の他、死亡保障を付けられる場合がある。インフレには弱い。
両方を併用した場合の老後資金シミュレーション(30年間)

前提:35歳から
・つみたて投資枠:月3万円(年間36万円)
・個人年金保険:月2万円(年間24万円)
【パターン1:標準ケース】
・つみたて投資枠(年4%):約2,019万円
・個人年金保険(返戻率105%):約756万円
・合計:約2,775万円
【パターン2:好調ケース】
・つみたて投資枠(年5%):約2,392万円
・個人年金保険(返戻率105%):約756万円
・合計:約3,148万円
【パターン3:低調ケース】
・つみたて投資枠(年2%):約1,460万円
・個人年金保険(返戻率102%):約734万円
合計:約2,194万円
年代別おすすめ配分例

・20〜30代前半:つみたて投資枠8割+個人年金保険2割(成長重視)
・30代後半〜40代:つみたて投資枠6〜7割+個人年金保険3〜4割(バランス型)
・50代〜退職前:つみたて投資枠4〜5割+個人年金保険5〜6割(安定重視)
今すぐできる資産形成ステップ
1.老後資金の目標金額と期間を決める
2.家計の余剰資金を確認する
3.つみたて投資枠で少額から長期運用を開始
4.個人年金保険で最低限の受取額を確保
5.年1回は積立額や配分を見直す
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



