個人年金保険
個人年金保険は払込免除特約をつけるべき?メリット・注意点と試算例をFPが解説

この記事では、個人年金保険に払込免除特約を付けるメリットと注意点、現実的な試算例を交えながら、必要かどうかの判断ポイントを独立系FPの視点で解説します。
個人年金保険の払込免除特約とは?仕組みと役割を解説

払込免除特約は、契約者や被保険者が一定の状態になった場合に、それ以降の保険料の支払いを免除する特約です。特約が適用されても契約はそのまま継続し、年金や満期金は契約通りに受け取れます。
一般的な免除条件は以下の通りです。
・所定の高度障害状態になった場合
・がん・急性心筋梗塞・脳卒中などの三大疾病と診断された場合
・公的介護制度で要介護2以上と認定された場合
ただし、条件や診断基準は保険会社によって異なります。契約前には必ず「どのような場合に免除になるのか」を約款や契約概要で確認しましょう。
個人年金保険の払込免除特約のメリット
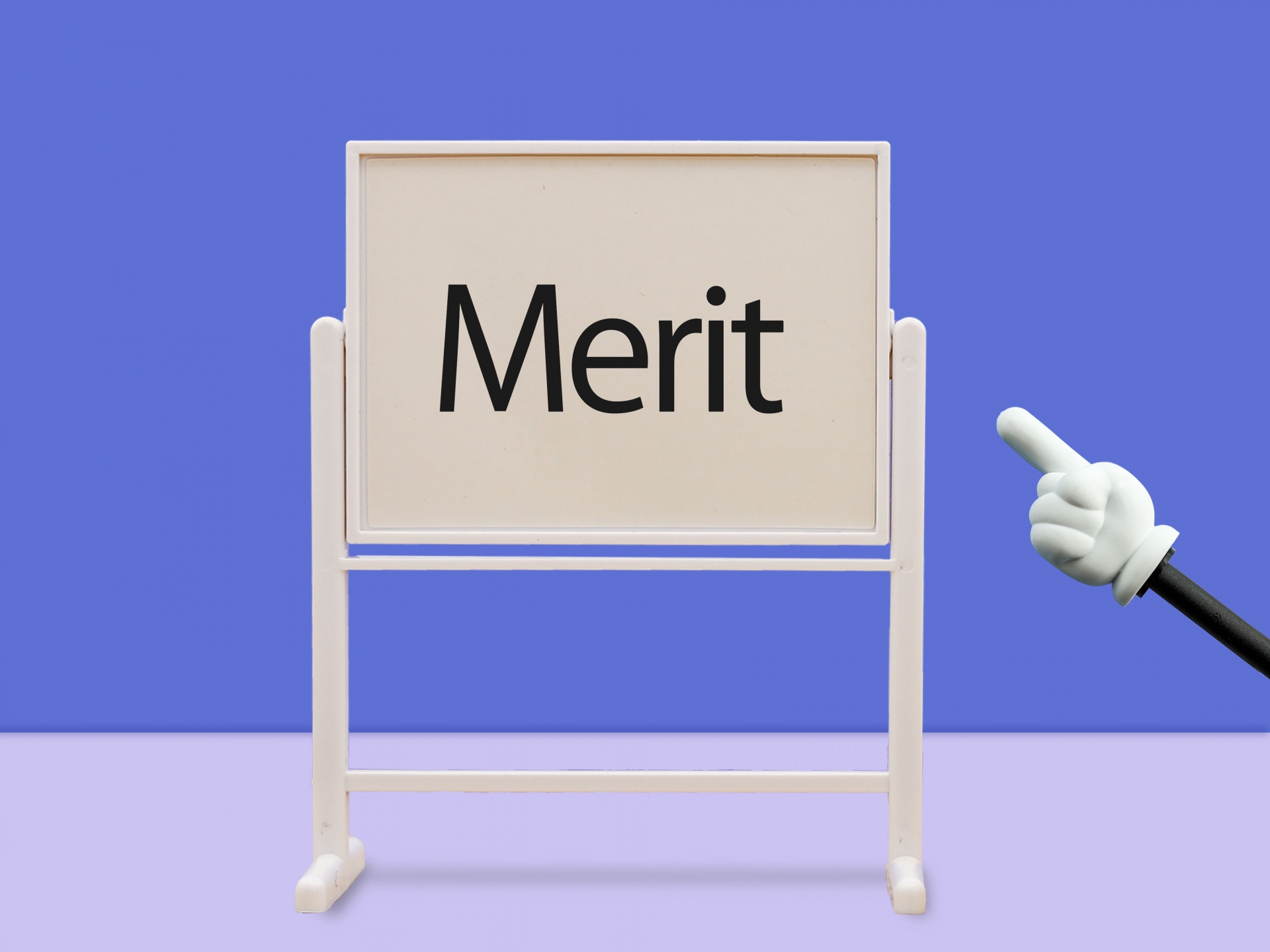
払込免除特約を付けることで保険料はやや増えますが、契約継続の安心感を得られます。ここでは主なメリットを3つにまとめます。
万が一のときでも老後資金を確保できる
・病気や事故で働けなくなっても契約は継続し、予定通りの年金が受け取れる
・保険料を支払えないリスクを回避できる
公的保障が手薄な人に安心感をもたらす
・長期契約の途中での中断リスクを減らせる
・自営業やフリーランスなど、公的保障が少ない層に特に有効
資産形成と保障を両立できる
・生命保険の保障機能と老後資金の積立を同時に実現
・長期の資産形成計画におけるリスク分散効果
個人年金保険の払込免除特約の注意点と契約前の確認事項

特約にはメリットがありますが、コストや条件面での注意も必要です。契約前に押さえておきたいポイントは次の通りです。
・保険料が上乗せされる(長期契約では総額が大きくなる)
・免除条件は会社ごとに異なる(診断基準や対象範囲の違いに注意)
・健康状態によっては契約時に特約を付けられない場合もある
これらを確認せずに契約すると、「せっかく付けたのに使えなかった」という事態になりかねません。
個人年金保険の払込免除特約を付けた場合の現実的な試算例

現行の低金利環境を前提に、35歳男性が個人年金保険に加入するケースを考えます。払込期間は20年、60歳から年間60万円を10年間(総額600万円)受け取る契約です。
月額保険料は約2万3,000円、総払込額は552万円、返戻率は約108%となります。
・特約なし:20年間で552万円を支払い、免除はなし
・特約あり(免除なし):月額約500円上乗せ、総払込額564万円
・特約あり(10年目に免除発生):払込は282万円で終了、その後も契約は継続し600万円を受取
免除が発生しない場合は返戻率がわずかに低下しますが、早期に免除が発生すれば負担軽減効果は非常に大きくなります。
個人年金保険の払込免除特約が必要かどうかの判断ポイント

払込免除特約の必要性は、働き方や公的保障の有無、家計の余裕度によって異なります。判断の目安は以下の通りです。
・収入の安定性(会社員で手当が充実していれば不要な場合も)
・公的保障や他の保険とのバランス
・老後資金準備の優先度と中断リスクの有無
・長期的に負担できる保険料水準
特に自営業やフリーランス、健康リスクを抱える人は、老後資金の積立を守るための有効な手段となります。
まとめ|個人年金保険の払込免除特約は条件と費用を比較して選ぶ
個人年金保険の払込免除特約は、予期せぬ事故や病気で働けなくなったときでも契約を維持し、老後資金を守るための「保険の中の保険」です。ただし、条件や費用を十分に理解し、自分の状況や保障とのバランスを踏まえて判断することが欠かせません。
長期の資産形成は「続けること」が最大のポイント。払込免除特約は、その継続を保険で支える有力な手段となります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



