個人年金保険
個人年金保険の途中解約は損?解約返戻金の仕組みと注意点

ここでは、解約返戻金の仕組みと注意点、解約以外の選択肢、年数別の返戻率の推移を例に、途中解約のリスクを分かりやすく解説します。
解約返戻金の仕組みと払込保険料との関係

個人年金保険を解約すると、保険会社から解約返戻金が支払われます。これは、それまでに払い込んだ保険料の一部が戻ってくるもので、金額は契約年数や商品設計によって異なります。
返戻金の算出には次の要素が関わります。
・払込済み保険料の総額
・保険会社の運用益
・事務コストや保険に付帯する保障部分のコスト
契約初期は、支払った保険料の多くが事務経費や手数料に充てられるため、返戻率は低くなります。一般的に返戻率が100%を超えるのは、契約から10年以上経過してからというケースが多いです。
元本割れのリスクと損をするケース

契約から数年以内に解約すると、元本割れのリスクが非常に高いです。例えば、3年間で総額120万円払った場合でも、解約返戻金が90万円程度しか戻らないことも珍しくありません。
損をする理由は、主に次のようなケースです。
・契約初期に発生する高額な契約費用
・運用が複利で増える前に解約することによる利息効果の消失
短期での途中解約は、資産形成の観点から見ても非効率です。やむを得ない場合を除き、解約は慎重に検討しましょう。
年数別返戻率の推移(例)

年間40万円の保険料を20年間払い込む契約を想定した場合、返戻率は次のような傾向を示します。
・契約初期(1〜3年目)は返戻率65〜75%程度と低く、元本割れが大きい
・10年目を過ぎる頃から返戻率は95%前後に近づき、損失は縮小
・20年目でようやく返戻率が110%を超え、元本超えとなる
グラフ化すると、契約前半は低い水準で推移し、後半にかけて右肩上がりとなる形が視覚的にわかります。
解約以外の選択肢

途中解約が損になると分かっていても、保険料の支払いが困難になることはあります。その場合、以下のような解約以外の選択肢も検討できます。
1.減額
保険金額を減らして保険料を下げる方法。返戻金は減りますが、契約は維持できます。
2.払済保険
それまで払い込んだ保険料を元に、保険金額を減額し、今後の保険料をゼロにする方法。保険期間は通常変わらず、将来受け取れる年金額が減るのが一般的です。途中解約よりは損失を抑えられる場合があります。
3.自動振替貸付制度の利用
解約返戻金を担保に保険料を立て替える制度。一時的に保険料の支払いを猶予でき、解約を回避できます。利息は通常、契約時の予定利率に数%を上乗せした水準となります。短期的な資金繰りには有効ですが、長期利用は負担が増えるため注意が必要です。
金利環境が与える影響
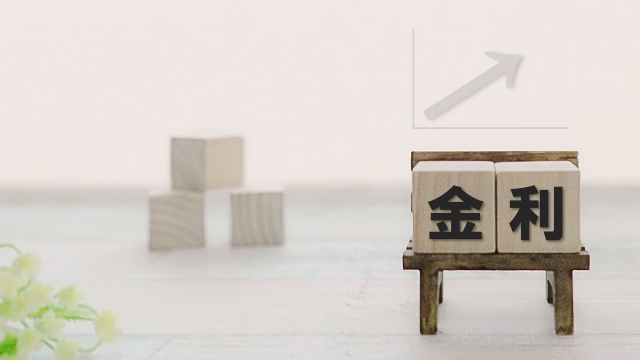
現在は低金利環境が長く続いており、多くの個人年金保険の予定利率は低い水準にあります。予定利率が低いと運用益が伸びにくく、長期的な積立効果が限定的になる可能性があります。契約前には、予定利率や運用の見込みも必ず確認しましょう。
税制面のポイント

個人年金保険は、契約内容によって個人年金保険料控除の対象になります。これにより、毎年の所得税や住民税の負担が軽減される場合があります。また、受取時には年金として受け取る場合は雑所得扱いで総合課税、一時金として受け取る場合は退職所得や一時所得として扱われるなど、受取方法によって課税方法が異なります。契約前に受取形態も含めて確認しておくことが重要です。
途中解約を避けるためのポイント
個人年金保険は長期的な資産形成を目的とした商品であり、契約満了まで継続することが最も効率的です。途中解約を避けるためには、次のポイントを意識しましょう。
・契約前にライフプランと保険料負担を慎重に試算する
・万一の収入減少時に備えて生活防衛資金を別に確保しておく
・保険料が負担になったら、すぐに解約ではなく減額や払済への切り替えを検討する
免責事項
ここで紹介した返戻率やシミュレーションはあくまで一例であり、実際の数値は保険会社や商品ごとに異なります。契約前には必ず約款や設計書で詳細を確認してください。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



