個人年金保険
個人年金保険と銀行預金の違いを徹底比較!確実性・利回り・選び方のポイント

この記事では、両者の特徴と利回りをわかりやすく比較し、さらに30年間のシミュレーション結果をもとに、あなたに合った選び方の判断基準を解説します。
銀行預金の特徴と利回り|元本保証と流動性の高さ

銀行預金は、元本保証と流動性の高さが最大の魅力です。特に預金保険制度によって、1金融機関につき元本1,000万円とその利息までが保護されます。
・安全性:ほぼリスクゼロ。金融機関が破綻しても、一定額まで保護。
・流動性:いつでも引き出せるため、急な出費にも対応可能。
・利回り:普通預金は年0.001〜0.002%程度、定期預金でも年0.002〜0.3%ほど(2025年現在)。
実質的には、金利による増加分はインフレ率に追いつかず、資産の購買力は目減りする可能性があります。老後資金を長期で運用する場合、安全性は高いが資産増加の効果は薄いといえます。
個人年金保険の特徴と返戻率|貯蓄と保障の両立

個人年金保険は、毎月または毎年保険料を積み立て、将来年金として受け取る仕組みです。保険会社によっては死亡保障や生存給付金がつく場合もあります。
・貯蓄性:契約期間中は解約返戻金が増えていき、満期時にまとまった年金原資になる。
・保障機能:契約者が死亡した場合、遺族に保険金が支払われるケースあり。
・返戻率:一般的に100〜110%前後(外貨建てや長期契約で120%超もあり)。
・流動性:途中解約すると高確率で元本割れ。特に契約初期の解約は払込保険料の半分以下になる場合もある。
返戻率は契約期間の長さや払込方法に左右され、長期積立でメリットが大きくなりますが、資金拘束が長く柔軟性に欠ける点には注意が必要です。
個人年金保険と銀行預金のシミュレーション比較

老後資金の準備方法によって、最終的な受取額は大きく変わります。今回は以下の条件でシミュレーションを行いました。
・毎月積立額:3万円
・積立期間:30年
・銀行預金金利:年0.002%(現実的な水準)
・個人年金保険返戻率:110%(30年後受け取り)
・併用:半分を銀行預金、半分を個人年金保険に積立
【シミュレーション結果(30年後)】
・銀行預金のみ:約1,080万円
・個人年金保険のみ:約1,188万円
・併用:約1,134万円
銀行預金は安全ですが、金利の低さから積立総額との差はほぼありません。個人年金保険は返戻率によって預金より多くなりますが、途中解約による損失リスクが大きい点を再確認しておきましょう。併用はその中間で、流動性と利回りをバランスよく確保できます。
個人年金保険と銀行預金、どちらを選ぶべきか
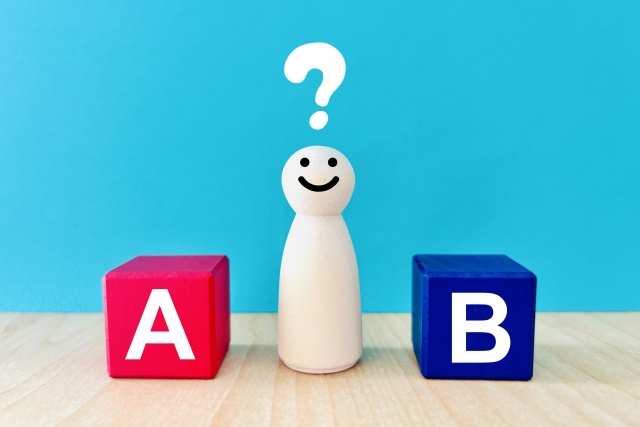
銀行預金と個人年金保険は、「安全性」か「増やす力」かで性質が異なります。
・安全性重視・短期利用
→ 銀行預金が有利。特に生活防衛資金や数年以内に使う予定の資金は預金で確保。
・老後資金の長期積立・計画的運用
→ 個人年金保険が有利。時間を味方にして返戻率を高められる。ただし途中解約のリスクを理解する必要あり。
また、どちらか一方だけでなく、預金と個人年金保険を組み合わせる分散戦略も効果的です。例えば、生活費2〜3年分は銀行預金に置き、それ以上の余裕資金は個人年金保険や他の長期運用商品に回す方法があります。
FP視点でのまとめ
・短期的な資金需要がある場合は銀行預金が有利
・老後資金の長期積立を確実に行いたい場合は個人年金保険が有利
・流動性と利回りのバランスを取りたい場合は併用がおすすめ
・他制度(NISA・iDeCo)も検討すれば、選択肢が広がる
実際の受取額はインフレ率や外貨建て年金の選択などによって大きく異なるため、最新の経済環境や為替動向も踏まえて計画を立てることが重要です。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



