相続
保有株式を相続財産として残す最適な方法|生前贈与・遺言書・節税対策を完全解説

保有している株式を相続財産として確実に承継させるためには、生前からの計画的な準備が欠かせません。上場株式・非上場株式を問わず、適切な方法を選択することで、相続税の負担を抑えつつ、確実な財産承継を実現できるでしょう。
本記事では、株式の相続における評価方法から、生前贈与・遺言書の活用、さらには税制優遇措置まで、国税庁などの公的機関の情報に基づき、実務で活用できる具体的な方法を解説していきます。
株式の相続における基本的な仕組み

株式の相続税評価額の算出方法
株式を相続する際には、相続開始時点(被相続人の死亡日)の時価で評価額を算出する必要があります。評価方法は上場株式と非上場株式で大きく異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
上場株式の評価方法
上場株式の相続税評価額は、以下の4つの価格のうち最も低い価格を採用します。
・相続開始日の最終価格(終値)
・相続開始月の毎日の最終価格の月平均額
・相続開始月の前月の毎日の最終価格の月平均額
・相続開始月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
この評価方法により、株価の一時的な変動による不公平を避けられるように配慮されています。証券会社に相続申告用の残高証明書を請求すれば、これらの株価が記載された資料を入手できるため、評価額の算出も比較的容易でしょう。
非上場株式の評価方法
非上場株式は市場価格が存在しないため、財産評価基本通達に従って評価します。評価方法は、株式を取得する人が「会社を経営する同族株主」か「それ以外の株主」かによって異なるのが特徴です。
原則的評価方式(同族株主などが取得する場合)では、会社の規模に応じて以下の方法を適用していきます。
・類似業種比準方式:類似業種の株価、配当金額、利益金額などから評価
・純資産価額方式:会社の純資産価額をもとに評価
・併用方式:上記2つを組み合わせた方式(中規模会社に適用)
特例的評価方式(経営に関与しない少数株主が取得する場合)では、配当還元方式により、年間配当金額を基準に評価額を算出します。
生前贈与を活用した株式承継の方法

暦年贈与による段階的な株式移転
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産が年間110万円以下であれば贈与税が非課税となる制度です。この基礎控除額を活用することで、長期的に株式を移転できるでしょう。
株式を暦年贈与で承継させる場合、贈与時の株式評価額が年間110万円以内に収まるように株数を調整することがポイントとなります。複数の受贈者(子や孫など)に贈与すれば、その人数分の基礎控除を活用できるため、より多くの株式を非課税で移転可能です。
暦年贈与の主なメリット:
・年間110万円までの贈与は贈与税が非課税
・複数の受贈者に贈与すれば、より多くの財産を非課税で移転できる
・計画的に実行することで、将来の相続財産を確実に減少させられる
出典:国税庁「No.4410 複数の人から贈与を受けたとき」
暦年贈与の注意点
暦年贈与を実施する際には、いくつかの注意点があります。まず、相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降の贈与については段階的に最長7年以内)に行った贈与は、相続財産に加算されて相続税の課税対象となる点に留意が必要です。
また、「定期贈与」とみなされないよう注意しましょう。最初から1,000万円を10年間で100万円ずつ贈与することを約束した場合、定期贈与と判断され、1,000万円に対して贈与税が課税される可能性があります。毎年新たに贈与契約を締結し、贈与契約書を作成しておくことが望ましいでしょう。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与について選択できる制度です。この制度を選択すると、累計2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。
令和6年1月1日以降の贈与からは、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除額については、贈与税が課税されないだけでなく、相続時の相続財産への加算も不要となるため、制度の利便性が大幅に向上しています。
相続時精算課税制度が適している主なケース:
・まとまった金額の株式を一度に贈与したい場合
・将来値上がりが予想される株式を早期に移転したい場合
・賃貸不動産に関連する株式(配当収入がある株式)を贈与する場合
ただし、一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻ることはできません。また、贈与財産は相続時に相続財産に加算されるため、直接的な節税効果は限定的です。選択にあたっては、慎重な検討が必要でしょう。
遺言書による株式承継の指定

遺言書作成の重要性
遺言書を作成しておくことで、自身の意思に基づいた株式の承継が可能となります。遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要となり、協議が難航すれば株式の名義変更手続きが滞るリスクがあるでしょう。
株式を遺言書に記載する際は、証券会社名・支店名・口座番号を明記することで、相続手続きをスムーズに進められます。非上場株式の場合は、会社名・本店所在地・株式の種類・株数を正確に記載することが重要です。
株式を記載する際の具体的な記載例
上場株式の記載例:
「遺言者は、遺言者が有する下記の株式を長男○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
・○○証券株式会社△△支店 口座番号:123456789
・銘柄:株式会社○○ 普通株式
・数量:1,000株」
非上場株式の記載例:
「遺言者は、遺言者が有する株式会社○○(本店:東京都○○区○○1-2-3)の普通株式500株を、長女○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。」
証券会社ごとに承継者を指定する方法
株式投資を行っている方の場合、保有銘柄の売却や新規購入により資産が変動する可能性があります。そのため、個別の銘柄を指定するのではなく、証券会社ごとに承継者を指定する方法が実務上は適しているでしょう。
例えば、「A証券会社の口座は長男に、B証券会社の口座は次男に」といった指定方法により、将来の資産変動にも柔軟に対応できます。各証券会社の保有資産に差が生じた場合は、生前に株式を売却・購入することで金額を調整することも可能です。
自筆証書遺言保管制度の活用
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、遺言書を安全に保管できるとともに、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。遺言書の作成には専門的な知識が必要となるケースも多いため、公正証書遺言の作成も含めて専門家に相談することをお勧めします。
非上場株式の事業承継税制

法人版事業承継税制の概要
非上場会社の株式を後継者に承継させる場合、法人版事業承継税制の活用により、贈与税・相続税の納税猶予を受けられる可能性があります。この制度には「一般措置」と「特例措置」の2種類があり、特例措置では納税猶予の対象となる株式数の制限が撤廃されています。
特例措置の適用を受けるためには、令和9年12月31日までに特例承継計画を都道府県に提出し、令和9年12月31日までに贈与・相続が行われることが要件となります。後継者の死亡などにより、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される点が大きな特徴です。
出典:国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」
株式の相続における実務上の注意点
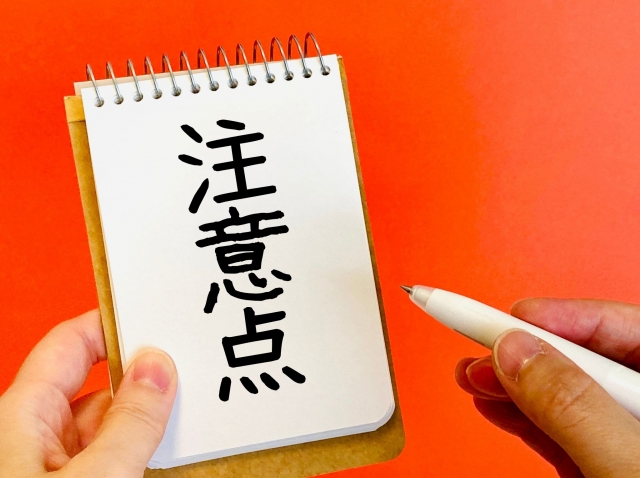
相続発生後の手続き
株式の相続が発生した場合、以下の手続きが必要となります。
・証券会社または信託銀行への連絡
・株式の評価額算定
・遺産分割協議の実施(遺言書がない場合)
・株式の名義変更手続き
・相続税の申告・納付(相続開始から10ヵ月以内)
被相続人が株式の売却により利益を得ていた場合や配当金を受け取っていた場合は、相続開始から4ヵ月以内に準確定申告を行う必要があります。
相続後に株式を売却する場合の税金
相続した株式を売却する場合、譲渡所得税(税率20.315%)が課税されます。相続した株式の取得費は、被相続人が取得した際の価額を引き継ぐことになるため、被相続人の購入時の価格を確認しておくことが重要です。
相続から3年10ヵ月以内に株式を売却した場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用できる可能性があります。この特例により、支払った相続税の一部を取得費に加算できるため、譲渡所得税の負担を軽減できるでしょう。
出典:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
株式承継の最適な方法を選択するためのポイント

相続までの期間を考慮する
相続までの期間が長く見込める場合は、暦年贈与を活用した段階的な株式移転が効果的です。年間110万円の基礎控除を長期間にわたり活用することで、多額の株式を非課税で承継できるでしょう。
一方、相続が比較的近い将来に発生する可能性がある場合や、まとまった金額の株式を一度に承継させたい場合は、相続時精算課税制度の活用を検討する価値があります。
株式の将来価値を予測する
将来的に株価の上昇が見込まれる株式については、早期に贈与することで、相続時の評価額を抑えられる可能性があります。相続時精算課税制度を利用すれば、贈与時の価額で相続税を計算するため、株価上昇による相続税の増加を回避できるでしょう。
複数の方法を組み合わせる
暦年贈与と相続時精算課税制度は、贈与者が異なれば併用が可能です。例えば、父親からの贈与には相続時精算課税制度を、母親からの贈与には暦年贈与を選択することで、それぞれのメリットを最大限に活用できます。
また、一部の株式は生前贈与で承継し、残りの株式は遺言書により承継を指定するといった方法も有効でしょう。
まとめ:計画的な準備で確実な株式承継を実現
保有株式を相続財産として残すための最適な方法は、株式の種類・評価額・相続までの期間・承継者の状況など、さまざまな要素を総合的に判断して決定する必要があります。
上場株式の場合は、暦年贈与や相続時精算課税制度を活用した生前贈与が効果的です。非上場株式の場合は、事業承継税制の特例措置を活用することで、大幅な税負担の軽減が期待できるでしょう。
いずれの方法を選択する場合でも、早期からの計画的な準備が成功の鍵となります。遺言書の作成により確実な承継を実現し、生前贈与により相続税の負担を軽減することで、次世代への円滑な財産承継が可能となるでしょう。
株式の相続は専門的な知識を要する分野であるため、税理士や弁護士などの専門家に相談しながら、それぞれの状況に最適な方法を選択することをお勧めします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



