iDeCo
会社員のiDeCo活用術:企業年金の種類で掛金上限が変わる?

「うちの会社、企業年金があるんだけど、iDeCoの掛金上限って変わるの?」
「転職したらiDeCoの手続きってどうなるの?」
会社員にとって、老後資金の準備は重要な課題です。iDeCo(個人型確定拠出年金)は、税制優遇を受けながら効率的に資産形成ができる強力な制度ですが、会社員のiDeCoには、加入している企業年金の種類によって掛金の上限額が変わるという特徴があります。また、転職時の手続きについても、事前に知っておくべき注意点が存在します。
この記事では、会社員がiDeCoを最大限に活用するためのポイントを解説します。企業型DCや確定給付企業年金(DB)の有無による掛金上限の違い、転職時のiDeCo移換手続きの注意点、そして会社員がiDeCoを活用するメリット(所得控除)を詳しくご紹介します。
会社員のiDeCo掛金上限は企業年金の種類で変わる

会社員がiDeCoに加入する場合、毎月拠出できる掛金の上限額は、勤務先の企業年金制度の有無や種類によって異なります。これは、公的年金に加えて企業年金という形で老後資金を準備している人とのバランスを取るためです。
企業年金がない会社員の場合
勤務先に企業年金(企業型DC、確定給付企業年金など)がない会社員は、iDeCoの掛金上限が月額2.3万円(年間27.6万円)です。
・特徴: 企業年金がない分、iDeCoで手厚く老後資金を準備できるよう、比較的高い上限額が設定されています。
・2025年度税制改正(予定): 2025年度には、この上限額が月額6.2万円(年間74.4万円)に大幅に引き上げられる予定です。これにより、企業年金がない会社員は、より大きな非課税メリットを享受しながら、老後資金を形成できるようになります。
企業型DC(確定拠出年金)に加入している会社員の場合
勤務先で企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入している会社員は、原則としてiDeCoにも加入できますが、掛金上限額が異なります。
・iDeCoの掛金上限: 月額2万円(年間24万円)です。
・注意点: 企業型DCの規約によっては、iDeCoに加入できない場合や、企業型DCの掛金とiDeCoの掛金の合計に上限が設けられている場合があります。事前に勤務先の人事・総務部門に確認が必要です。
・法改正(2022年10月〜): 以前は企業型DCに加入しているとiDeCoに加入できないケースがありましたが、法改正により、原則としてiDeCoへの加入が可能になりました。
確定給付企業年金(DB)に加入している会社員の場合
勤務先で確定給付企業年金(DB)に加入している会社員も、iDeCoに加入できます。
iDeCoの掛金上限: 月額1.2万円(年間14.4万円)です。
2024年12月改正: 2024年12月からは、この上限額が月額2万円(年間24万円)に引き上げられました。これにより、DB加入者もiDeCoをより活用しやすくなっています。
公務員の場合
公務員も、確定給付型の年金制度に加入しているため、上記3の確定給付企業年金(DB)に加入している会社員と同様の掛金上限が適用されます。
iDeCoの掛金上限: 月額2万円(年間24万円)です(2024年12月改正後)。
転職時のiDeCo移換手続きの注意点
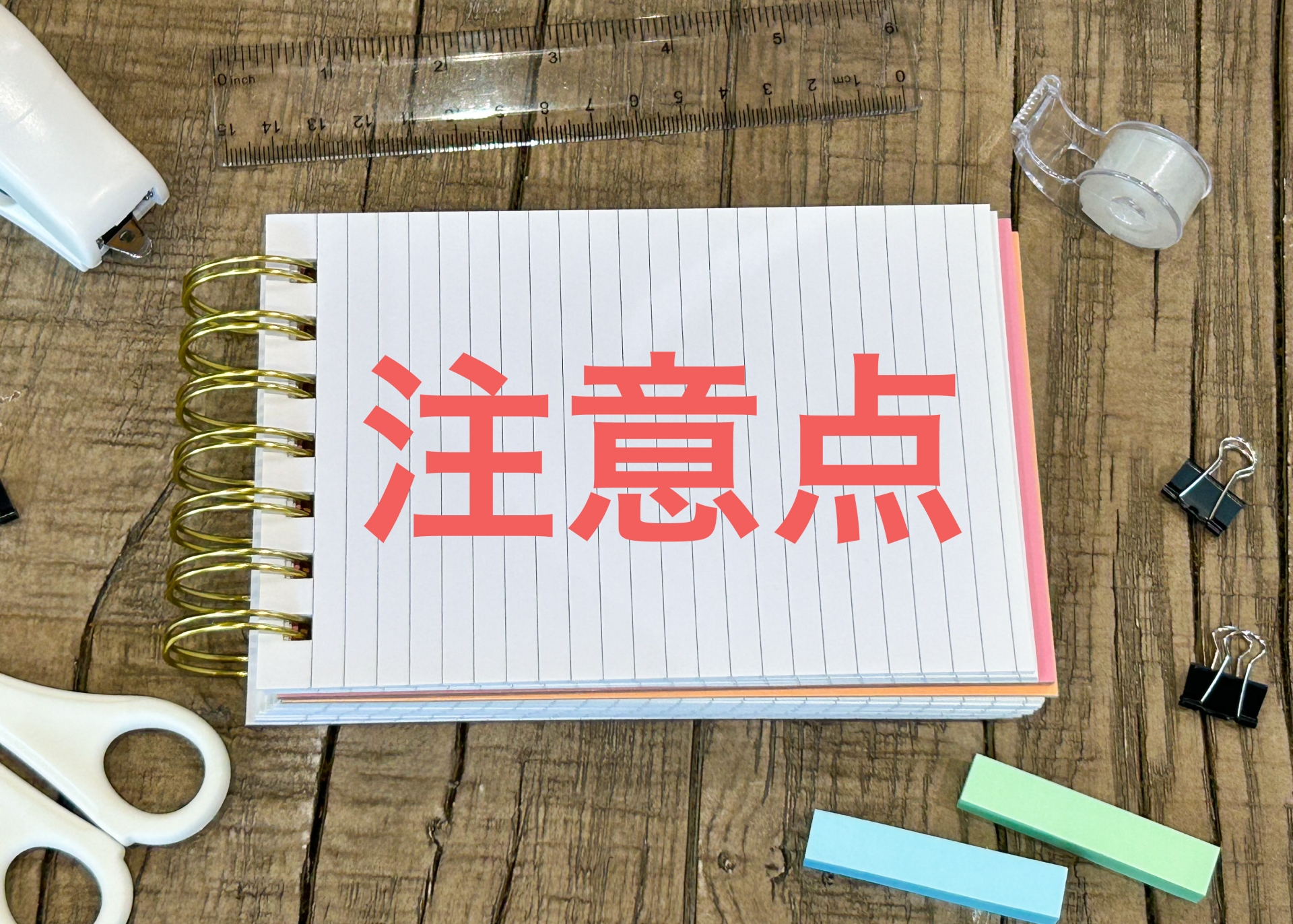
会社員が転職する場合、iDeCoの資産を新しい勤務先の状況に合わせて移換する手続きが必要です。この手続きを怠ると、資産が国民年金基金連合会に自動移換され、手数料がかかったり、運用が停止されたりするリスクがあります。
転職先の企業年金制度を確認する
転職が決まったら、まず転職先の企業年金制度(企業型DCの有無、確定給付企業年金の有無など)を確認しましょう。これにより、新しい勤務先でのiDeCoの掛金上限額や、企業型DCとの兼ね合いが決まります。
移換手続きの種類
転職先の企業年金制度によって、iDeCoの資産の移換方法は主に以下の3つです。
・転職先の企業型DCへ移換: 転職先に企業型DCがあり、iDeCoからの移換を受け入れている場合。
・iDeCoのまま継続: 転職先に企業年金がない、またはiDeCoの継続が可能な場合。掛金上限額が変わる可能性があります。
・他の金融機関のiDeCoへ移換: 転職を機に、現在利用しているiDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更したい場合。
移換手続きの注意点
・手続きの期限: 転職後、原則として6ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると、資産が国民年金基金連合会に自動移換されてしまいます。
・自動移換のリスク: 自動移換された場合、資産は現金で管理され運用が行われず、年間一定の手数料がかかります。また、再度iDeCoや企業型DCで運用を開始する際に、別途手続きが必要になります。
・必要書類の確認: 移換手続きには、転職先の証明書や、iDeCoの運営管理機関からの書類など、複数の書類が必要になります。事前に確認し、漏れがないように準備しましょう。
・専門家への相談: 転職時のiDeCo手続きは複雑に感じることもあります。不安な場合は、iDeCoの運営管理機関やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。
会社員のiDeCo活用メリット(所得控除)
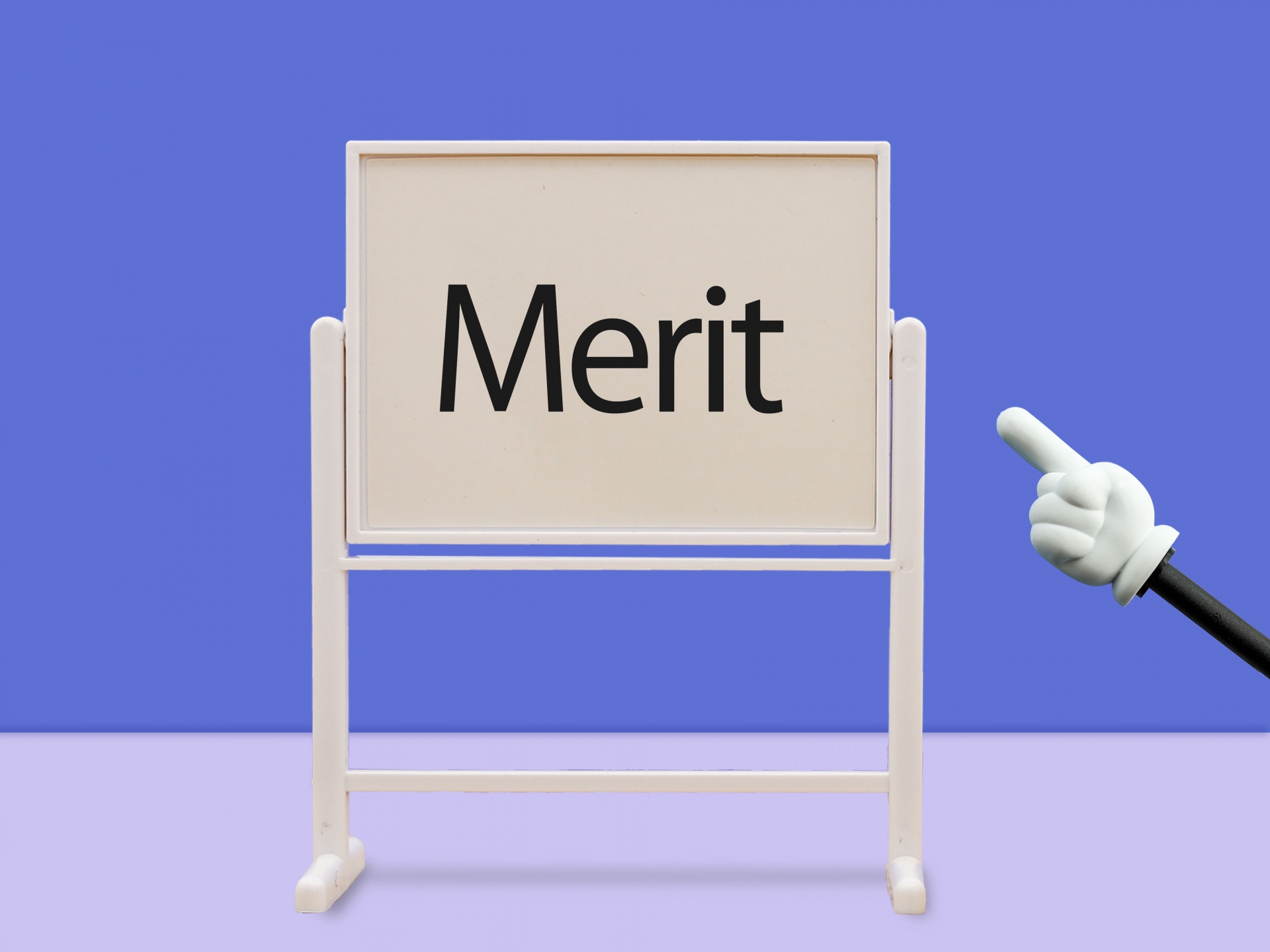
会社員がiDeCoを活用する最大のメリットは、掛金が全額所得控除になることです。これは、NISAにはないiDeCo独自の強力な税制優遇であり、現役時代の家計に直接的な恩恵をもたらします。
所得税・住民税の軽減効果
iDeCoに拠出した掛金は、その年の所得から全額差し引かれます。これにより、課税所得が減り、所得税と住民税が軽減されます。
計算例:
・年収500万円の会社員(所得税率10%、住民税率10%)が、iDeCoに月額2.3万円(年間27.6万円)拠出した場合。
・年間節税額:27.6万円 × (所得税率10% + 住民税率10%) = 5万5,200円
毎年5万5,200円が税金として戻ってくる、または翌年の税金が安くなる計算です。
年末調整・確定申告での手続き
会社員の場合、iDeCoの掛金控除は年末調整で手続きが可能です。
・手続き: 毎年10月頃に国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を勤務先に提出することで、年末調整で控除が適用されます。
・確定申告: 年末調整に間に合わなかった場合や、個人事業主・フリーランスの方は確定申告で手続きを行います。
運用益も非課税
iDeCoのもう一つの大きなメリットは、運用中に得た利益(運用益)が非課税になることです。通常、投資信託などの運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoではこの税金がかかりません。これにより、効率的に資産を増やし、複利効果を最大限に享受できます。
まとめ:会社員こそiDeCoを賢く活用しよう
会社員にとって、iDeCoは老後資金準備の強力なツールです。勤務先の企業年金の種類によって掛金上限は異なりますが、その違いを理解し、ご自身の状況に合わせた最適な掛金設定を行うことが重要です。
また、転職時にはiDeCoの移換手続きを忘れずに行い、せっかく築いた資産を無駄にしないよう注意しましょう。
iDeCoの最大の魅力である「掛金全額所得控除」と「運用益非課税」のメリットを最大限に活用し、計画的に老後資金を準備することで、安心してセカンドライフを迎えることができるでしょう。ぜひ、ご自身の企業年金制度を確認し、iDeCoの活用を検討してみてください。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています



