火災保険
事業用火災保険の法人契約|個人契約との違いと実務上の重要ポイント

法人が所有・使用する事業用物件は、火災や自然災害による損害が発生すると事業継続に直結します。
本記事では法人契約の基本、個人契約との違い、地震補償の制限や動産補償の限度、免責金額・経費計上まで、実務視点で解説します。
法人名義で火災保険を契約できるケース

法人名義で火災保険を契約できるのは、法人が実際に事業活動に利用している建物や資産です。本社や営業所などのオフィスはもちろん、工場や倉庫も契約対象となります。
さらに、法人が借りているテナントやレンタルオフィスも、法人名義で契約が可能です。建物そのものだけでなく、空調や給排水設備などの附属設備、機械設備や在庫品も補償対象に含められます。
個人契約と法人契約の主な違い
火災保険には個人契約と法人契約があり、補償対象や評価方法に違いがあります。個人契約は生活用の財産を守ることを目的としていますが、法人契約は事業用の建物や設備、商品などを補償するのが特徴です。
個人向けの火災保険では、建物・家財の評価は再調達価額(新価)が基本で、時価で契約している火災保険は少なくなっています。
一方、法人向け火災保険では、工場設備や機械など高額な事業資産が対象となるため、時価評価額か再調達価額を選択することができます。保険料を抑える目的で時価を選ぶケースもありますが、事業再開を優先する場合には再調達価額で契約するのが一般的です。
事業用物件で火災保険を契約する際の注意点
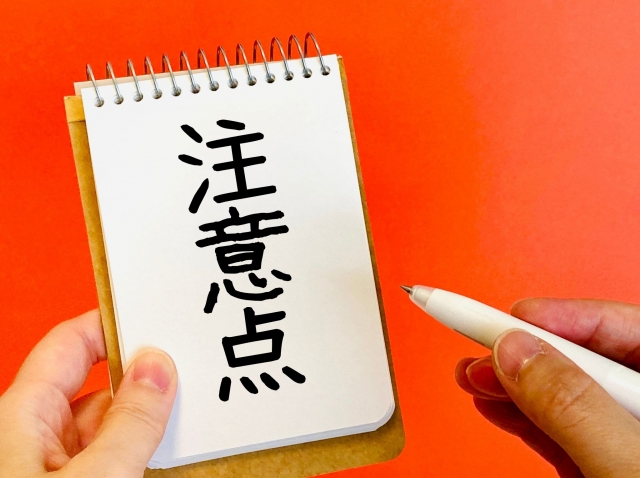
地震補償の制限とBCP対策
まずBCP対策について説明します。BCPとは「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略称で、災害や事故が発生した際に事業への影響を最小限に抑え、早期復旧を図るための計画や取り組みのことです。火災保険における地震補償は、このBCP対策の重要な要素となります。
事業用の建物には、個人住宅向けの地震保険は適用されません。法人が地震リスクに備えるには、火災保険に「地震危険補償特約」(地震拡張担保特約とも呼ばれる)を付帯する必要があります。
この特約は、地震・噴火・津波による火災、損壊、流失、埋没など地震に関連するあらゆる損害を包括的に補償します。契約方式には「縮小支払方式」と「支払限度額方式」があり、自社のリスク状況に応じて選択できます。
法人が地震危険補償特約に加入する場合、建物の構造や立地条件によっては保険会社による個別審査が必要になることがあります。まずは保険会社や代理店に相談し、加入可能性の確認と加入に向けたアドバイスを受けることから始めましょう。
動産補償の限界
動産も補償対象に含められますが、限度があります。現金は通常20〜30万円が上限であり、それを超える金額はカバーされません。また、100万円を超える高額な什器や在庫も対象外となる場合があります。こうした資産を守るには、別途、資産ごとに動産総合保険への加入を検討する必要があります。
補償されない資産
法人契約の火災保険でも、すべてが対象になるわけではありません。営業車両や配送車などの自動車、帳簿やソフトウェアといった情報資産、移動中の物品などは補償対象外です。これらは法人向けの自動車保険や運送保険など、別の保険で対応しなければなりません。
免責金額の設定
火災保険には自己負担額である免責金額を設定できます。例えば、免責を10万円に設定すればそれ以下の損害は自己負担となりますが、保険料を抑えることができます。自社の資金体力や損害発生の頻度を考慮し、適切な水準を決めることが重要です。
経費計上の扱い
法人が支払う火災保険料は原則として全額を経費に計上できます。ただし、契約期間が2年以上に及ぶ場合には前払費用として計上し、会計年度ごとに按分する処理が必要です。会計処理を誤ると税務上のリスクにつながるため、経理部門と連携して適切に処理しましょう。
利益保険・休業補償の活用
火災保険が建物や設備の修理費を補償するのに対し、利益保険(休業補償特約)は操業停止による売上減少や人件費・家賃などの固定費をカバーします。たとえば工場が火災で1か月操業できなかった場合、火災保険で修理費を補い、利益保険で売上減少や従業員給与をカバーすることで、資金繰りを安定させることが可能です。
複数物件の包括契約
事業所や社宅を複数抱える法人は、物件ごとに契約するよりも包括契約を利用すると効率的です。包括契約にすることで経理処理や保険料管理が一括で行え、更新時の手間も大幅に軽減されます。大規模法人ほどこのメリットを享受しやすいでしょう。
契約期間と更新の工夫
法人火災保険は1年契約が基本ですが、最長5年の長期契約も可能です。長期契約は料率改定の影響を受けにくく保険料も割安になる傾向があります。ただし、資産状況の変化に補償内容を合わせにくいというデメリットもあるため、更新時には資産の増減やリスク状況を踏まえて見直しを行うことが不可欠です。
ただし、事業活動総合保険のような商品では、保険期間中に店舗や施設が増えても自動的に補償対象に含まれる場合があるため、代理店や保険会社に相談してみましょう。
多店舗展開しているような業種では、1店舗ずつバラバラに保険に加入するより、全店一括でカバーする保険に加入したほうが、満期管理も楽になります。
まとめ:事業用物件のリスクを適切にカバーする
法人契約による火災保険は、事業継続に不可欠なリスク管理の手段です。建物や設備に加え、地震特約や利益保険を組み合わせることで幅広いリスクに対応できます。さらに、包括契約の活用や免責金額のバランスを考えることで、災害リスクに強い法人経営を実現することができます。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



