ニーサ
NISAのリバランスは必要?資産配分の見直しで効率的な運用

「NISAで積立投資を始めたけど、一度買ったらあとは放置でいいの?」
「ポートフォリオが崩れてるって聞くけど、どうしたらいいの?」
NISAは長期投資が基本ですが、一度設定したポートフォリオ(資産の組み合わせ)をそのままにしておくと、いつの間にかリスクが高まっていたり、効率が落ちていたりする可能性があります。そこで重要になるのが「リバランス」という作業です。
この記事では、NISA運用において定期的なポートフォリオの「リバランス」が必要かどうか、そしてその具体的な方法を徹底解説します。リバランスの目的(リスク調整、目標リターンの維持)、適切な頻度、具体的な手順まで、あなたのNISA運用をより効率的に維持するための知識を提供します。
なぜNISAのリバランスが必要なのか?ポートフォリオが崩れる理由

NISAで投資を始めた際、あなたは株式と投資信託を50%ずつ、といったように、目標のリスク許容度に合わせて資産の配分を決めたはずです。しかし、時間が経つとこの比率は自然と崩れていきます。
例えば、株価が大きく値上がりすると、ポートフォリオ全体に占める株式の割合が増え、当初よりもリスクの高い状態になってしまうことがあります。逆に、特定の資産が大きく値下がりすれば、その割合が減ってしまい、期待していたリターンが得られにくくなるかもしれません。
リバランスとは、このように崩れてしまった資産の比率を、再び当初決めた理想の割合に戻すことを指します。
リバランスの主な目的
1.リスクの調整・維持:
値上がりした資産を売却し、値下がりした資産を買い増すことで、ポートフォリオ全体のリスクを当初の許容範囲内に保ちます。これにより、想定外の大きな損失を防ぎやすくなります。
2.目標リターンの維持:
最適な資産配分を維持することで、長期的に目標とするリターンを得られる可能性を高めます。
3.「安い時に買い、高い時に売る」の実践:
リバランスは結果的に、値下がりした資産を買い足し(安く買い)、値上がりした資産を売却する(高く売る)という、投資の基本を自動的に実践することにつながります。
NISAのリバランスは必要?結論とメリット
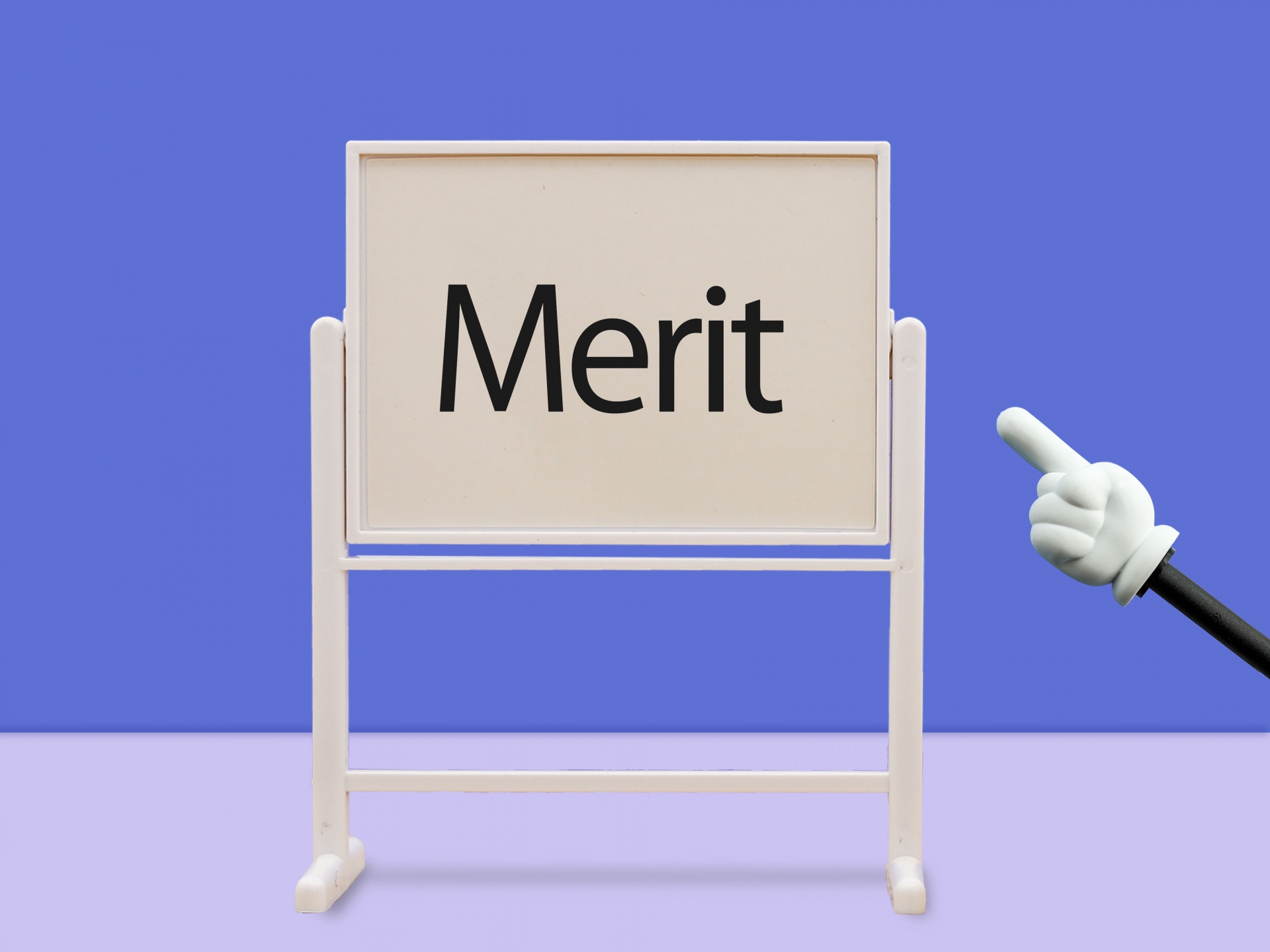
結論から言うと、NISA運用においてリバランスは「必要」な場合が多いです。特に、複数の資産クラス(例:株式と債券)や、複数の地域(例:国内株式と外国株式)に分散して投資しているポートフォリオであれば、その必要性は高まります。
リバランスのメリット
・リスクコントロール: ポートフォリオが特定の資産に偏ることを防ぎ、リスクを当初設定したレベルに保てます。
・効率的な運用: 資産配分を最適に保つことで、長期的なリターンの安定と最大化に寄与します。
・感情に左右されない投資: 定期的に行うことで、市場の変動に感情的に反応して売買するのを避けられます。
・新NISAのメリットを活かす: 新NISAでは、売却した非課税枠が翌年に復活します。リバランスで利益を確定しつつ、その枠を再利用できるため、柔軟に資産配分を調整できます。
ただし、リバランスには手間がかかる点や、売買手数料が発生する可能性がある点(NISA口座内の売買手数料が無料の金融機関を選べばコストは抑えられます)も考慮に入れる必要があります。
NISAのリバランス、適切な「頻度」は?
リバランスの頻度に厳密な正解はありませんが、一般的には以下のいずれかの方法で行われます。
1.定期的に行う(時間軸):
・半年に1回、または1年に1回:最も一般的で実践しやすい頻度です。決まった時期(例:年末、お給料日後など)にチェックする習慣をつけるのがおすすめです。
・毎年1回: 忙しい方でも無理なく継続できる頻度です。新NISAの年間投資枠も毎年リセットされるため、このタイミングでの見直しも有効です。
2.資産配分の乖離(かいり)率で行う(乖離率軸):
・当初設定した資産配分から、特定の資産の割合が±5%や±10%以上乖離した場合に行う方法です。この方法は、市場の変動が大きい時に効果的ですが、常にポートフォリオをチェックする必要があり、手間がかかります。
結論として、初心者は、まず「年に1回」といった定期的なリバランスから始めるのがおすすめです。
NISAのリバランス、具体的な「手順」と方法

リバランスには主に2つの方法があります。
方法1:売買によるリバランス(推奨)
これが最も一般的な方法です。値上がりして比率が増えた資産の一部を売却し、その資金で値下がりして比率が減った資産を買い増すことで、元の比率に戻します。
【手順】
1.現在のポートフォリオの確認:
NISA口座を開設している金融機関のウェブサイトやアプリで、保有している各資産の評価額と、ポートフォリオ全体に占める割合を確認します。
2.理想の資産配分との比較:
当初設定した理想の資産配分(例:株式60%、債券40%)と、現在の配分を比較します。
3.売却と買い増し:
・値上がりして比率が上がった資産(例:株式)の一部を売却します。
・売却で得た資金と、もし可能であれば新規の資金で、値下がりして比率が下がった資産(例:債券や、まだ足りない分の株式)を買い増します。
・新NISAでは、売却した投資元本分の非課税枠が翌年以降に復活します。これにより、非課税メリットを継続しつつ、柔軟にリバランスが可能です。
方法2:積立額調整によるリバランス(手間が少ない)
毎月の積立投資を行っている場合に有効な方法です。資産の売買を行わず、今後の積立額の配分を調整することで、徐々に理想の比率に戻していきます。
【手順】
1.現在のポートフォリオの確認:同様に現在の資産配分を確認します。
2.理想の資産配分との比較:理想の配分と現在の配分を比較します。
3.今後の積立額を調整:比率が少なくなってしまった資産(例:債券)に対して、今後の積立額を多めに設定したり、ボーナス投資を活用したりして、徐々に比率を上げていきます。
・メリット: 売買の手間や手数料(もしあれば)がかかりません。
・デメリット: 完全に比率を戻すまでに時間がかかる場合があります。
まとめ:NISAのリバランスで効率的な「ほったらかし」運用を
NISAのリバランスは、資産形成を成功させるための重要な要素です。一度ポートフォリオを作ったらそれで終わりではなく、定期的に見直し、調整していくことで、リスクを適切に管理し、効率的な運用を続けることができます。
特に新NISAの柔軟な非課税枠と期間無期限というメリットは、リバランスと非常に相性が良いです。年に1回程度の簡単な見直しからで大丈夫です。あなた自身の最適な頻度と方法を見つけ、NISA運用を「賢くほったらかし」できる状態を維持していきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。



