iDeCo
NISAとiDeCoはどっち優先?併用で最強の老後資金を作る方法

この記事では、新NISAとiDeCoの具体的な違いを比較しながら、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。そして、あなたのライフステージや資産状況に合わせた最適な併用戦略を提案し、最強の老後資金を築くための実践的なアプローチをご紹介します。
新NISAとiDeCoを賢く使いこなし、将来の不安を解消しましょう。
新NISAとiDeCo、それぞれの特徴と基本的な違いを再確認
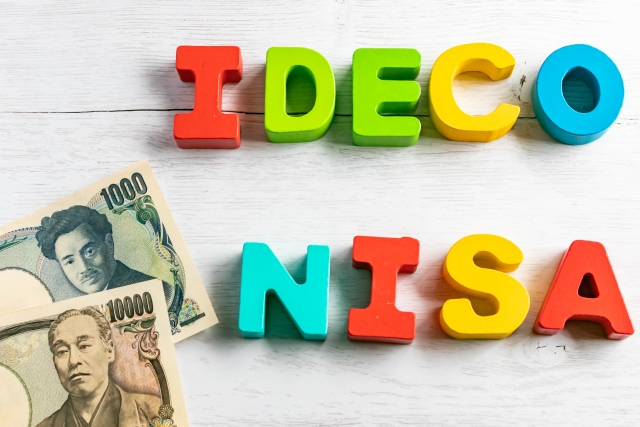
まずは、新NISAとiDeCo、それぞれの制度が持つ基本的な特徴と、投資を行う上で知っておくべき違いを明確に理解しましょう。
新NISA(少額投資非課税制度)とは?
新NISAは、2024年から始まった、誰もが利用できる非課税投資制度です。
・つみたて投資枠:年間120万円まで
・成長投資枠:年間240万円まで
・年間合計:360万円まで
・生涯投資枠:1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
・非課税期間:無期限
・投資対象:投資信託、ETF、個別株など(成長投資枠)
・資金の引き出し:いつでも可能
・売却後の非課税枠復活:売却した投資元本分の非課税枠は、翌年以降に再利用可能
新NISAのポイントは、自由度が高く、投資対象も幅広い点です。教育資金や住宅購入資金など、ライフイベントに合わせた柔軟な資金形成に適しています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?
iDeCoは、自分で掛金を拠出し、自ら運用商品を選んで運用する私的年金制度です。
・掛金の上限
<企業年金に加入していない会社員、専業主婦(夫)など>:月額2.3万円(年額27.6万円)
<企業型DCや確定給付年金(DB)に加入している会社員、公務員など>:月額2万円(年額24万円)
<自営業者など>:月額6.8万円(年額81.6万円)
※企業年金の掛金相当額によっては、iDeCoの掛金上限が2万円を下回る場合や、iDeCoに加入できない場合もあります。
・非課税期間:拠出期間中、運用期間中
・投資対象:投資信託、定期預金、保険など(金融機関によって異なる)
・資金の引き出し:原則60歳以降
・税制優遇:
<掛金が全額所得控除>所得税・住民税が軽減されます。
<運用益が非課税>通常課税される運用益が非課税です。
<受取時も税制優遇>公的年金等控除や退職所得控除の対象となります。
iDeCoのポイントは、老後資金形成に特化した制度であり、強力な税制優遇が魅力です。特に、掛金が全額所得控除になる点は、現役世代にとって大きなメリットとなります。ただし、原則60歳まで引き出せない制約があります。
新NISAとiDeCo、徹底比較!メリット・デメリット

それぞれの制度の概要を把握したところで、具体的なメリット・デメリットを比較し、より深く理解していきましょう。
比較項目ごとの違い
【目的】
・新NISA:幅広いライフイベント資金、資産形成
・iDeCo:老後資金形成に特化
【年間上限額】
・新NISA:360万円(つみたて120万+成長240万)
・iDeCo:職業・企業年金有無で異なる(月2万円~6.8万円)
【非課税期間】
・新NISA:無期限
・iDeCo:拠出・運用期間中
【投資対象】
・新NISA:投資信託、ETF、個別株など幅広い
・iDeCo:投資信託、定期預金、保険(限定的)
【資金拘束】
・新NISA:いつでも引き出し可能
・iDeCo:原則60歳まで引き出し不可
【税制優遇】
・新NISA:運用益・売却益が非課税
・iDeCo:1. 掛金全額所得控除、2. 運用益非課税、3. 受取時も税制優遇
【口座管理費】
・新NISA:基本無料(証券会社による)
・iDeCo:必要(金融機関による)
【売却枠復活】
・新NISA:あり(翌年以降)
・iDeCo:なし
新NISAのメリット・デメリット

【メリット】
・資金の流動性が高い:必要になったらいつでも引き出せるため、教育資金や住宅購入資金など、将来のライフイベントにも対応できます。
・非課税期間が無期限:非課税の恩恵を永続的に受けられます。
・投資対象が幅広い:投資信託だけでなく、個別株やETFなど、ご自身の投資戦略に合わせて自由に選択できます。
・売却後の非課税枠復活:資金が必要で一度売却しても、枠が復活するため再度利用できる柔軟性があります。
・運用益・売却益が非課税:利益に対して税金がかからないため、効率的に資産を増やせます。
【デメリット】
・掛金の所得控除がない:iDeCoのように掛金が所得控除の対象にならないため、現役世代の節税効果はiDeCoに劣ります。
・口座管理費等:証券会社によっては、一部の手数料が発生する場合があります。(ただし、多くのネット証券ではNISA口座の維持手数料は無料です)
iDeCoのメリット・デメリット
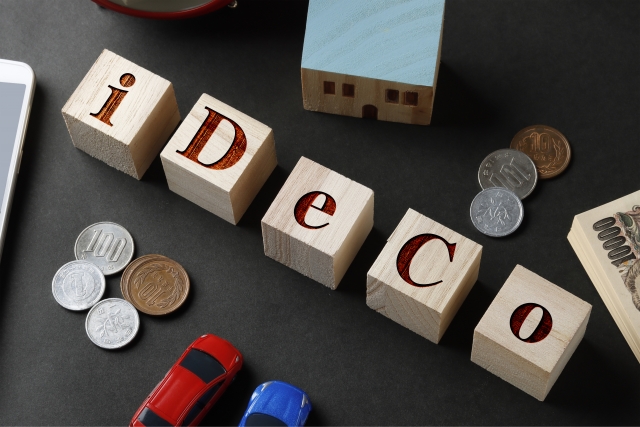
【メリット】
・掛金が全額所得控除:拠出した掛金は全額所得控除の対象となり、所得税・住民税を軽減できます。これがiDeCo最大のメリットと言えるでしょう。
・運用益が非課税:運用期間中に得た利益には税金がかかりません。
・受取時も税制優遇:60歳以降に受け取る際も、公的年金等控除や退職所得控除といった税制優遇が適用されます。
・老後資金に特化:強制的に資金がロックされるため、途中で使ってしまう心配がなく、計画的に老後資金を準備できます。
【デメリット】
・原則60歳まで引き出し不可:途中で急な出費が必要になっても、原則として60歳まで資金を引き出すことはできません。
・口座管理手数料がかかる:運営管理機関(金融機関)や国民年金基金連合会、信託銀行に毎月手数料を支払う必要があります。
・投資対象が限定的:新NISAに比べて投資対象が投資信託、定期預金、保険商品に限定されます。
・元本確保型商品ではメリットが少ない:定期預金などの元本確保型商品を選ぶと、運用益非課税のメリットがほとんど活かせません。
あなたはどっち優先?目的別・年代別優先順位
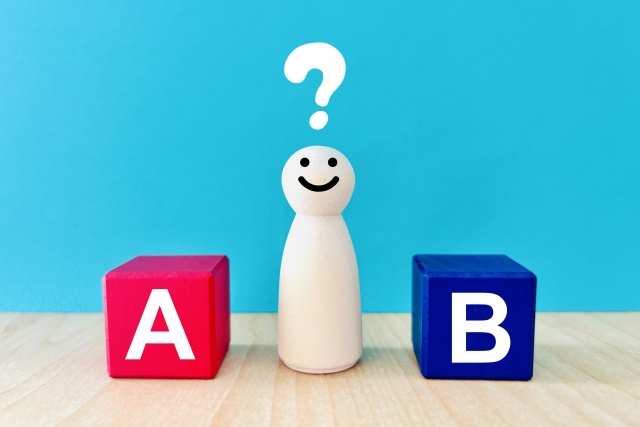
新NISAとiDeCoはどちらも優れた制度ですが、あなたの状況によって優先順位は異なります。目的別、そして年代別にどちらを優先すべきか、具体的なケースで見ていきましょう。
とにかく現役時代の税金を安くしたい!
iDeCo優先:iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となるため、所得税・住民税を直接軽減する効果があります。課税所得が高い人ほど、その恩恵は大きくなります。
将来のライフイベント資金も準備したい(教育資金、住宅購入資金など)
新NISA優先:新NISAは資金の引き出しがいつでも可能です。将来の様々なライフイベントに備える資金形成に適しています。
老後資金だけを確実に貯めたい!途中で引き出す心配がない方が良い
iDeCo優先:原則60歳まで引き出せない制約が、かえって資金を確実に貯める強制力となります。
運用益を非課税にしたい!
どちらも有効:新NISAもiDeCoも運用益が非課税になるため、どちらの制度でもこのメリットを享受できます。
年代別優先順位

20代~30代(若年層):iDeCo→新NISAの順に検討
【iDeCo優先の理由】
・所得控除の恩恵:働き始めでまだ収入が少なくても、所得控除によって税負担が軽くなるのは大きなメリットです。
・運用期間の確保:早くから始めれば、60歳までの運用期間が長く取れるため、複利効果を最大限に享受できます。
・強制力:若いうちは誘惑も多いため、原則引き出せないiDeCoで確実に老後資金を確保する習慣をつけるのがおすすめです。
新NISAの活用:iDeCoの掛金を拠出しつつ、余剰資金で新NISAのつみたて投資枠から利用し、教育資金や住宅購入など将来のライフイベントに備えましょう。特に、年間360万円の枠を若いうちに使い切ることで、非課税運用の期間を長く取れます。
40代~50代(中年層):新NISAとiDeCo、両方を積極的に活用
・iDeCoの活用:所得控除による節税効果は引き続き大きいため、掛金上限まで拠出を検討しましょう。老後までの期間が短くなる分、より確実な運用を意識することが大切ですし、2024年12月の制度改正で掛金上限が月額2万円に引き上げられた方は、さらに節税効果を高めるチャンスです。
・新NISAの活用:子どもの教育費や住宅ローンなど、まとまった資金が必要になる時期です。新NISAの資金の流動性の高さを活かし、ライフイベントに合わせた資金を確保しつつ、成長投資枠も活用して資産形成を加速させましょう。
60代以降(高年層):新NISAをメインに活用
・iDeCo:原則60歳で新規の掛金拠出は終了します。これまでに積み立てたiDeCo資産を、適切なタイミングで受け取り、税制優遇を最大限に活用しましょう。
・新NISA:iDeCoの掛金拠出が終わっても、新NISAは生涯投資枠(1,800万円)を使い切るまで利用可能です。退職金などのまとまった資金がある場合、非課税期間が無期限の新NISAに移管(※課税口座からの移管)したり、新規投資をすることで、老後資金の取り崩しをしながらも運用益非課税の恩恵を受け続け、資産寿命を延ばすことができます。
最強の老後資金を作る!新NISAとiDeCoの最適な併用戦略

新NISAとiDeCoは、それぞれ異なる強みを持つため、単独で使うよりも併用することで、より効率的かつ強力に老後資金を形成できます。
節税と非課税運用の両取り!基本的な併用ステップ
ステップ1:iDeCoの掛金上限まで拠出を検討
・まずはiDeCoの「掛金全額所得控除」という最大のメリットを享受するために、無理のない範囲で掛金上限まで拠出することを検討しましょう。特に課税所得が高い人ほど、この恩恵は大きいです。
・金融機関によっては、iDeCoの口座管理手数料を無料にしているところもあるため、手数料の低い金融機関を選ぶことが大切です。
ステップ2:iDeCoで非課税になった所得から新NISAへ投資
・iDeCoの掛金で節税できた分、手元に残るお金が増えます。その増えたお金を、今度は新NISA口座で運用しましょう。
・新NISAは年間360万円と大きな投資枠があるため、つみたて投資枠(年間120万円)からコツコツと積み立てを始めるのがおすすめです。
ステップ3:ライフステージに合わせて投資配分を調整
・若いうちはリスクを取ってリターンを狙える全世界株式やS&P500などのインデックスファンドを中心に、iDeCoと新NISAの両方で積立投資を行いましょう。
・年齢が上がるにつれて、iDeCoは老後資金の確実性を重視した運用にシフトし、新NISAはライフイベントの資金と老後資金のバランスを考慮した柔軟な運用を心がけましょう。
シミュレーションで見る併用効果
例えば、課税所得500万円の会社員(企業年金なし)が、毎月2.3万円(年間27.6万円)をiDeCoに拠出し、さらに年間120万円を新NISAのつみたて投資枠で運用した場合を考えてみましょう。
・iDeCoの節税効果:
所得税率20%、住民税率10%とすると、年間27.6万円の30%(所得税5.52万円+住民税2.76万円)=約8.28万円の税金が軽減されます。
所得税は国税庁のサイト、住民税は総務省のサイトより参照(所得割のみの概算で計算しています。)
・新NISA・iDeCo共通の非課税運用益:
仮に年間3%で運用できた場合、通常なら20.315%の税金がかかる運用益が丸々非課税になります。長期で運用すればするほど、この複利効果の恩恵は非常に大きくなります。
このように、iDeCoで節税し、新NISAで柔軟に運用益を非課税にするという二段階の構えで、資産形成を強力に推進できます。
運用商品の選び方と注意点
iDeCoの運用商品:
・原則60歳まで引き出せないため、長期的な視点で世界経済の成長に連動するインデックスファンド(例:全世界株式、S&P500)を選ぶのが王道です。
・手数料が低い「信託報酬が低い」ファンドを選びましょう。
新NISAの運用商品:
・つみたて投資枠は、iDeCoと同様に長期・積立・分散投資に適したインデックスファンドがおすすめです。
・成長投資枠では、個別株やETF、高配当株などを組み入れることで、より積極的な運用も可能です。
ポートフォリオのバランス:
・iDeCoと新NISA、両方で同じような商品に偏りすぎないよう、全体のバランスを考慮しましょう。例えば、iDeCoで全世界株式、新NISAでS&P500をメインにするなど、少し分散させることも考えられます。
・無理のない範囲で、ご自身の年齢やリスク許容度に合わせた配分を心がけましょう。
まとめ:NISAとiDeCoで、未来をデザインする賢い資産形成を
新NISAとiDeCoは、それぞれ異なる魅力を持つ優れた資産形成制度です。
・iDeCoは、現役時代の節税効果と、老後資金の確実な準備に強みを発揮します。
・新NISAは、高い自由度と非課税枠の柔軟性で、様々なライフイベントに対応しながら効率的な資産形成が可能です。
どちらか一方を優先するのではなく、両者のメリットを最大限に活かした「併用戦略」こそが、最強の老後資金、ひいては豊かな人生を築くための鍵となります。
ご自身のライフプランや資産状況に合わせて、最適なバランスを見つけ、今日から新NISAとiDeCoを賢く活用し、安心して暮らせる未来をデザインしていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。



