iDeCo
iDeCoのスイッチングとは?運用商品の見直しで資産を増やす方法

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、一度選んだ運用商品を原則60歳まで変更できないと思われがちですが、実は違います。あなたのiDeCo資産を効率的に増やしていくために、「スイッチング」という重要な機能があります。これは、運用中の商品を別の商品に乗り換えることで、市場の変化や自身のライフステージに合わせてポートフォリオを見直すことができる仕組みです。
この記事では、iDeCoのスイッチングの仕組みと目的を詳しく解説します。さらに、スイッチングのメリット・デメリット、どんな時にスイッチングすべきかの判断基準、そして似たような言葉であるポートフォリオのリバランスとの違いまでを深掘りします。賢くスイッチングを活用し、iDeCoの資産を増やしていきましょう。
iDeCoの「スイッチング」とは?その仕組みと目的

スイッチングとは、iDeCoで現在保有している運用商品を売却し、その資金で別の運用商品を買い付けることです。簡単に言えば、運用中の「商品入れ替え」や「乗り換え」を指します。
例えば、これまで株式型の投資信託で運用していた資産の一部、または全部を、定期預金や債券型の投資信託に変更するといったことが可能です。
スイッチングの主な目的
1.運用方針の見直し:
市場環境の変化(例:株式市場が過熱しすぎていると感じる時)や、景気サイクルの変化に対応して、よりリスクの低い商品へ変更したり、あるいは成長が期待できる他の資産クラスへ移行したりします。
2.リスクの調整:
年齢を重ねるごとにリスク許容度が下がる傾向があります。そうしたライフステージの変化に合わせて、株式比率を減らし、債券や元本確保型の割合を増やすことで、ポートフォリオ全体のリスクを調整します。
3.商品の改善:
現在保有しているファンドよりも、さらに信託報酬(運用コスト)の低い、または運用成績が良いファンドが新たに登場した場合に、そちらに乗り換えることで、長期的なリターンを改善できます。
スイッチングのメリット・デメリットと手数料

スイッチングには利点がある一方で、注意すべき点も存在します。
スイッチングのメリット
・柔軟な運用が可能になる: iDeCoの運用は長期にわたりますが、スイッチングがあることで、途中で運用方針やリスクを調整できます。
・市場の変化に対応できる: 相場が大きく動いた際、ポジションを見直してリスクを減らしたり、チャンスを活かしたりできます。
・コストの最適化: より低コストな運用商品に乗り換えることで、長期的に運用コストを削減し、手取りリターンを増やすことができます。
スイッチングのデメリット・注意点
・タイミングの見極めが難しい: 市場の先行きを完全に予測することは困難です。売却後に株価が上昇したり、乗り換えた商品が期待通りのパフォーマンスを発揮しなかったりするリスクがあります。
・手数料が発生する場合がある:
【主な手数料】
信託財産留保額: 一部の投資信託では、換金する際に「信託財産留保額」という手数料がかかる場合があります。これは売却代金から差し引かれる費用です。
運用管理機関による手数料: ごく一部の金融機関では、スイッチングの際に独自の事務手数料が発生することがあります。事前に確認しておきましょう。
新たな商品の購入手数料: スイッチング後の新たな商品の購入に手数料がかかることは、iDeCoでは基本的にはありませんが、念のため確認が必要です。
・スイッチングが反映されるまでのタイムラグ: 注文を出してから実際に売買が完了し、反映されるまでに数日から1週間程度かかることがあります。その間の市場変動リスク(価格変動リスク)は避けられません。
・頻繁なスイッチングは避ける: 短期的な市場の変動に一喜一憂して頻繁にスイッチングを行うと、手数料負担が増えるだけでなく、かえって運用成績を悪化させる可能性があります。
どんな時にスイッチングすべきか?判断基準
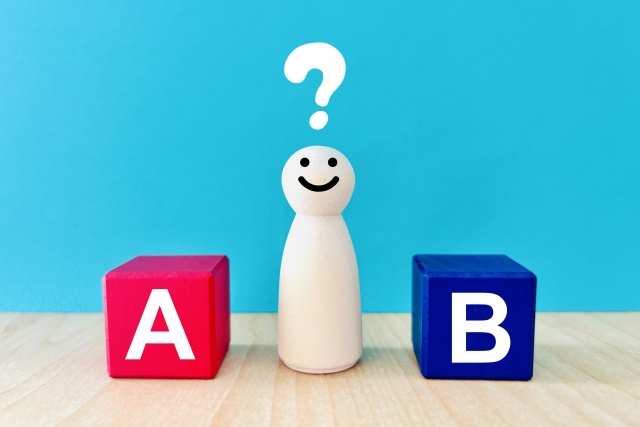
スイッチングは有効な手段ですが、頻繁に行うべきではありません。以下のタイミングで検討すると良いでしょう。
ライフステージの変化
あなたの年齢や家族構成、将来の計画が変わった時は、リスク許容度を見直す良い機会です。
【例】
・リタイアが近づいてきた時: 株式などのリスク資産の比率を減らし、元本確保型や債券型の比率を増やすことで、資産の目減りを防ぎ、安定した受け取りに備えます。
・収入が大きく変わった時: リスク許容度が上がった(下がった)場合、ポートフォリオの比率を見直します。
市場環境の大きな変化
特定の資産クラスが過度に値上がり(または値下がり)し、当初設定したポートフォリオのバランスが大きく崩れてしまった時です。
【例】
・株式市場が大幅に上昇しすぎた場合: 株式型の投資信託の比率が上がりすぎている場合、その一部を売却し、債券型や元本確保型にスイッチングすることで、リスクを調整します。
・特定の地域や資産が長期的に低迷している場合: その資産の将来性を見極め、回復が見込めない、または他に魅力的な投資先がある場合にスイッチングを検討します。
運用商品の「質」が改善された時
現在保有しているファンドよりも、さらに低コストで運用効率が良いファンドが新たに登場した場合です。
【例】
・同じ指数に連動するインデックスファンドで、信託報酬がより低いファンドが提供された場合。
・より長期的な視点で魅力的な新しい資産クラスやテーマのファンドが登場した場合。
「スイッチング」と「ポートフォリオのリバランス」の違い

スイッチングと似た言葉に「ポートフォリオのリバランス」があります。どちらも運用商品の見直しを行いますが、その意味合いには違いがあります。
・スイッチング:
保有している特定の運用商品を、別の運用商品に「交換する」ことを指します。主に運用管理機関が提供する運用商品の種類を変える際に使われます。
・ポートフォリオのリバランス:
運用している資産全体の「比率」を、当初設定した理想的な配分に戻すことを指します。例えば、株式が値上がりして比率が増えた分を売却し、債券など値下がりして比率が減ったものを買い増すことで、元の比率に戻す行為です。リバランスの中に、スイッチングという手段が含まれることもあります。
iDeCoでは、掛金拠出時に指定する商品の比率を変更する機能と、すでに積み立てた資産をスイッチングする機能の二つがあります。リバランスは、この両方の機能を組み合わせて行う総合的な資産配分調整の考え方です。
まとめ:iDeCoのスイッチングで、柔軟な資産運用を
iDeCoのスイッチング機能は、長期にわたる運用の中で、市場環境やあなたのライフステージの変化に合わせて、ポートフォリオを柔軟に見直すための重要なツールです。
・原則60歳まで引き出せないiDeCoだからこそ、スイッチングで柔軟性を持たせる。
・メリット(柔軟な運用、コスト最適化)とデメリット(手数料、タイミングの見極め)を理解する。
・ライフステージの変化や市場の大きな変動時など、必要なタイミングで実施する。
・頻繁なスイッチングは避け、冷静な判断を心がける。
賢くスイッチングを活用し、あなたのiDeCo資産を最適な状態で運用し続けることで、安心できる老後資金の準備を着実に進めていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています



